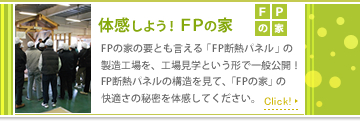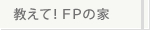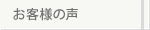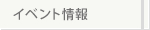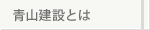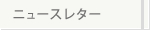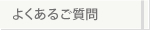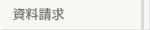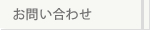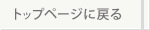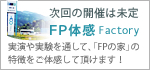農地を宅地に転用して、分家住宅を建築したプロジェクトである。いつか農地を相続するご長男の方がクライアントだ。地目を変更することで納税がどの程度増すのかを確認しながら、宅地にする面積を無駄なく決めることから設計は始まった。
「平屋」で「隣地にある実家との関係性をうまく構築できる家」というのがクライアントの大きな要望だった。単純に平屋にするのは簡単だ。けれど、基礎や屋根の面積が大きくなるので総予算は増加する。「本当に平屋が必要なのか??」という議論を何度も行った。
子供部屋の広さをある程度確保しながら3部屋。更に、仏間付きの和室やしっかりした広さの洗濯物を干すスペースを計画するとかなり大きな面積が必要になる。何度も何度も議論を重ね、デザインや予算を考慮しながら辿り着いたのは、寝室と仏間付きの和室・外部空間と繋がる洗濯物が干せるスペースを1階へ、3つの子供部屋を2階という2階建て案だ。
隣地にある実家との関係性の構築という課題に対して、当初の模型では西側の道路に開けたような形で、東側のご実家に裏口が繋がるようなイメージでプレゼンした。しかし、その案とは逆である東側(ご実家側)に開き、大きく繋がるような計画をご両親方は望まれた。
「さて、どうしたものか」…僕はクライアントの奥様と隣地のご実家との関係性が良い距離感になるような、家の配置やプランにしたかった。かといって、土地を提供していただくご実家の意見は蔑ろには出来ない。思案は何度も何度も頭の中で繰り返された。
その結果、玄関は西側の道路から直接アクセス出来るように配置し、ご実家からの視界に入らないよう建物自体を折り曲げることで死角を作り出すことにした。仏間のある和室や庭と繋がる洗濯干し土間空間は、積極的にご実家と繋がるようにした。けれど、リビングやダイニングはその庭と繋がる土間空間を緩衝空間として、間接的に繋がるように意識をした。
和室や土間空間が東側に来ることで、道路に近い西側には寝室が必然的に配置される。西側の日射による負荷や、道路からの視線などは寝室に取り入れたくない。けれども、道路から眺めるおうちの造形デザインは、この寝室部分が一番重要になる。結果、急な勾配屋根に鋭く配置したガラス部分による「光」で寝室を構成することとした。
和室から土間空間→ダイニング→キッチン→リビングと繋がる1階の部屋は、実際よりとても広く感じることが出来る。そこに、縦につながる吹き抜けと大きな開口部が、空間が広がりすぎないように観た感覚をギュッと締める。土間部屋は洗濯干しだけでなく、机や椅子を移動することで食事をしたりリラックスしたり多様に使える空間にもなる。建具を閉めた空間と開けた空間…その両方で違った顔を見せる。
クライアントの2つの大きな要望は、この設計により叶えることが出来たのではないかと考える。けれど、使い方を限定したり生活の仕方を固定化したりせず、お子さんが巣立った後もご実家との関係が新しいものになった場合も、この家が今度はご実家と呼ばれるような日が来ても、柔軟に永く住んでもらえるのではないだろうか。
「平屋」で「隣地にある実家との関係性をうまく構築できる家」というのがクライアントの大きな要望だった。単純に平屋にするのは簡単だ。けれど、基礎や屋根の面積が大きくなるので総予算は増加する。「本当に平屋が必要なのか??」という議論を何度も行った。
子供部屋の広さをある程度確保しながら3部屋。更に、仏間付きの和室やしっかりした広さの洗濯物を干すスペースを計画するとかなり大きな面積が必要になる。何度も何度も議論を重ね、デザインや予算を考慮しながら辿り着いたのは、寝室と仏間付きの和室・外部空間と繋がる洗濯物が干せるスペースを1階へ、3つの子供部屋を2階という2階建て案だ。
隣地にある実家との関係性の構築という課題に対して、当初の模型では西側の道路に開けたような形で、東側のご実家に裏口が繋がるようなイメージでプレゼンした。しかし、その案とは逆である東側(ご実家側)に開き、大きく繋がるような計画をご両親方は望まれた。
「さて、どうしたものか」…僕はクライアントの奥様と隣地のご実家との関係性が良い距離感になるような、家の配置やプランにしたかった。かといって、土地を提供していただくご実家の意見は蔑ろには出来ない。思案は何度も何度も頭の中で繰り返された。
その結果、玄関は西側の道路から直接アクセス出来るように配置し、ご実家からの視界に入らないよう建物自体を折り曲げることで死角を作り出すことにした。仏間のある和室や庭と繋がる洗濯干し土間空間は、積極的にご実家と繋がるようにした。けれど、リビングやダイニングはその庭と繋がる土間空間を緩衝空間として、間接的に繋がるように意識をした。
和室や土間空間が東側に来ることで、道路に近い西側には寝室が必然的に配置される。西側の日射による負荷や、道路からの視線などは寝室に取り入れたくない。けれども、道路から眺めるおうちの造形デザインは、この寝室部分が一番重要になる。結果、急な勾配屋根に鋭く配置したガラス部分による「光」で寝室を構成することとした。
和室から土間空間→ダイニング→キッチン→リビングと繋がる1階の部屋は、実際よりとても広く感じることが出来る。そこに、縦につながる吹き抜けと大きな開口部が、空間が広がりすぎないように観た感覚をギュッと締める。土間部屋は洗濯干しだけでなく、机や椅子を移動することで食事をしたりリラックスしたり多様に使える空間にもなる。建具を閉めた空間と開けた空間…その両方で違った顔を見せる。
クライアントの2つの大きな要望は、この設計により叶えることが出来たのではないかと考える。けれど、使い方を限定したり生活の仕方を固定化したりせず、お子さんが巣立った後もご実家との関係が新しいものになった場合も、この家が今度はご実家と呼ばれるような日が来ても、柔軟に永く住んでもらえるのではないだろうか。