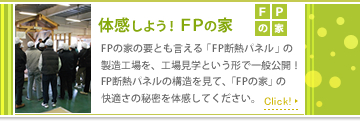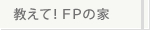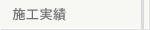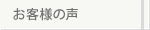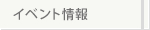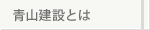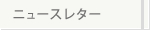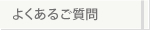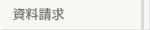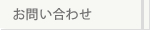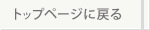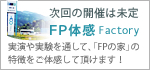2019年12月26日
2019年12月20日
「メタセコイアのなぐさめ」
団地の敷地内に、ひろびろと芝生が張ってある。わたしが住む5階からそこへ降り立ったのは、過去7年のうちに、ほんの数回。
ベランダからうっかり落としてしまった植木鉢を拾いにいったり、風に舞った洗濯物を慌てて追いかけていったり――。
つまり、不測の事態に対応すべく、慌てふためいて5階から駆け下りていったのであった。
本当ならば、日当たりが抜群の芝生の上で、梅干などを思いっきり干したい。
1階の住人の生活がベランダから丸見えなので、共有スペースとはいえ、立ち入りを遠慮してしまうのだ。
しかし、この奥ゆかしき遠慮とは一切無縁なものがただ一人、芝生の上を自由闊達に飛び跳ねている。
隣の団地に住む、メス猫のゆきちゃんだ。ここはもはや、ゆきちゃんが独占するパラダイス。
何かがおかしい――、と猫に対して思ったところで仕方がない。
人間であるわたしは、自由気ままにパラダイスを独り占めする彼女に、羨望の眼差しを投げかけることしかできないでいる。
ここには、5階建ての団地を優に越す、3本のメタセコイアの大木が立っている。
わたしが住む5階のリビングの窓は、四季の移り変わりと共に、姿を変えてゆくメタセコイアを映し出す額縁となっている。
12月に入り、メタセコイアの葉が黄金色に輝きはじめた。
大きな額縁には、空と光と、黄金の葉が輝いている。わたしとメタセコイアは、地上から数メートル離れた空中で、密やかで静かな関係性を保っているのだった。
この数週間というもの、心と目線が、樹木の足元へ投げかけられている。
それは、柿の葉の落ち葉拾いから始まった。
落ち葉を拾うには、目線を落し、歩調をゆるめ、美しい存在に、すべての意識を集中させなければならない。心と頭から忙しさを取り除き、美しいものを拾い上げるために、純粋な時間を奉げるのだ。なんて贅沢なひとときなのだろう。
立ち止まり、呼吸をゆるめ、子供の目線、自然と対等な場所にまで降り立ってゆき、その美しさと向き合う。やがて、自然はこちらにそっと手を差し伸べる。
柿の葉は、銀杏の葉を拾えとささやき、銀杏の葉は、紅葉の葉を手にしろと呟く。
赤く染まった紅葉の葉に触れた時、わたしは団地の芝生に転がる、メタセコイアの実を拾い上げようと決めたのだった。
冬空の下、防寒着で全身を厚く固めたわたしは、芝生へと降りていった。
草のベッドに気ままに転がる、幾つもの幾つものメタセコイアの実に導かれるまま、わたしは身を低くかがめ、無言のなぐさめを拾い上げてゆく。
わたしは最近、「きのこのなぐさめ」(ロン・リット・ウーン著、みすず書房)という本を読んでいる。
最愛の夫を突然の死で失った女性が、森の中で出会うきのこを通して、悲しみに塞がれていた暗い世界から、光の世界への扉を開けてゆく、ノルウェーを舞台にした再生の物語だ。
自然の中に身をゆだねると、日常のわたしを幸運にもどこかに置き忘れ、目線を落した草に、拾い上げる実に近しい存在となってゆく。
草も、実も、木も、わたしも、みな平等の位置に並んでいるのだ。
それは、「神のなぐさめ」と言ったらいいのかもしれない。
猫のゆきちゃんが、草むらを思うがままに飛び跳ねるように、わたしは転がる木の実と夢中になって戯れる。ゆきちゃんのパラダイスは、わたしのパラダイスでもあったのだ。
黄金色に葉を染める12月のメタセコイアのなぐさめを、わたしは地上と空中で、無心になって拾い上げる。
2019年12月17日
 基礎断熱はネオマフォームに壁断熱はセルローズファイバー、そして屋根断熱もネオマフォーム、サッシはYKKAPの「APW330」という高断熱住宅物件です。
基礎断熱はネオマフォームに壁断熱はセルローズファイバー、そして屋根断熱もネオマフォーム、サッシはYKKAPの「APW330」という高断熱住宅物件です。自分の設計の際には基礎断熱を採用しない私ですが、床下に冬季用エアコンを設置して暖気を床下から上げる基礎断熱特有の温熱計画にはとても魅力を感じます。
2019年12月13日
「カレーは炒めなくてもいい」
台湾の鶏スープ「山薬鶏湯(シャンヤオジータン)」を作った。手羽元に干しナツメ、ネギのぶつ切り、そして、本来なら山芋を入れるところをレンコンで代用し、水、酒、塩、生姜と共に、鍋にふたをして煮込むだけ。
あっさりとしていて、しかし滋味深く、心とからだにじわじわと優しく沁みこんでゆくスープだ。鍋いっぱいに作ったのはいいが、連日この淡白な味がつづくと飽きがくる。
そこで、しょう油を加え、片栗でとろみを付けておかずにしようと、ガスコンロの前に立った途端、何故だか無性にカレーが食べたくなった。
鶏と野菜の旨みが滲み出たスープだ。
ここに、カレー粉とルーを入れるだけで、カレーらしくはなるだろうと思い、軽く煮込んでみた。それが、どうしたことだろう。
玉ねぎを茶色になるまで根気よく炒め、にんにくや生姜、もろもろの野菜を次々と加え炒め、肉を入れて、云々かんぬん――と、幾つものステップを踏んでゆく王道の炒めカレーよりも、この思いつき簡単カレーの方が、よっぽど美味しく、しかもあっさりとして後味がいい。
何で今まで、こんな簡単なことに気がつかなかったのだろう。
台湾式スープから生まれた展開料理に味を占め、今度は台湾のよだれ鶏「口水鶏(コウシュイジー)」を作った。
鶏胸肉1枚を鍋に入れ、肉がしっかり浸かるように水を足す。
肉を取り出し、鍋の水を沸騰させ、沸いたら食べやすい大きさに切った肉を入れ、弱火にする。ふたをして10分程度ゆでたら火を止め、ふたをしたまま、冷めるまで余熱で肉の中まで火を通す。
一枚肉のままだと火が入りにくいので、食べる際の大きさに切って調理した方が安心だ。
冷めた肉を、にんにくと生姜のすりおろし、しょう油、砂糖、酢の、いわゆる南蛮だれで和え、刻みネギを散らして頂く。
大根のおろし汁に一晩漬けておいた胸肉を使ったので、とにかく食感がほろりと柔らかい。
箸がとまらない味とは、正にこのことで、白米が進む直球の美味さだ。
この料理、南蛮だれで和えてもいいが、先ほどの炒めないカレーや、ラーメンスープの土台など、いかようにも展開できる、優秀なベース料理となる。
冬に入ってから、冷蔵庫にもやしと大根のナムルを欠かさないようにしている。
豆もやしを茹でてざるに上げ、冷ましたもの(決して水にさらしたり、しぼったりしてはいけない!)と、太めに千切りした大根に塩をして、水分をしぼったものをボールに合わせる。
にんにくのすりおろし、ごま油、塩、炒りゴマ、酢、砂糖、顆粒の鶏がらスープを加え、調味料が万遍なく野菜に馴染むように、手でよく混ぜ合わせ、ガラス容器に入れてストックしておく。
ほうれん草があれば、更に美味しく、色彩豊かなナムルとなる。
ナムルのストックがあると、先ほどのラーメンに乗せたり、甘辛い口水鶏に和えたりと、抜群の応用力で、食卓に栄養と味覚のバランスを豊かに彩ってくれるのだ。
充填豆腐を買ったまま、冷蔵庫で賞味期限が過ぎてしまったが、処分するには忍びない。
一体、どうしたらよいものか?
冷蔵庫を開ければ、くだんの充填豆腐に、もやしと大根のナムル、口水鶏とゆで汁の残りがある。これ、酸辣湯(サンラータン)の材料だ――。
ゆで汁に、裂いた胸肉、もやしと大根のナムル、一口大に切った充填豆腐、ネギ、椎茸、黒酢、黒胡椒、塩、ラー油、しょう油を加えて煮る。
口水鶏のゆで汁で作る酸辣湯は、今まで食べたことのない優しい味わい。すべての素材が仲良く手をつなぎ、平和と安泰が器の中に満たされている。
賞味期限を過ぎた充填豆腐は、何の悔いも残さず、天寿を全うしたにちがいない。わたしは、安堵の思いで器を満たす汁を飲み干した。
胸肉が安いときにまとめ買いをし、大根のおろし汁に一晩漬け込んでおく。
口水鶏のように蒸し煮にして、ゆで汁と一緒に冷凍保存すれば、様々な料理に展開ができる。これで夕食の支度が楽になるだけでなく、食卓のバリエーションが豊かになる。
胸肉を細かく裂き、フライドオニオンとともに白米に乗せ、鶏皮をしょう油、砂糖、少しの塩で混ぜたたれをかける台湾の「鶏肉飯(ジーロウファン)」ができるし、シンプルに照り焼き、野菜をたっぷり加えたトマトソース煮、炊き込みご飯やミネストローネ、シチュー、バンバンジー、サラダ、などなど――。
さて、どこまで展開出来るだろう。
2019年12月6日
「点と面から、香りとデザインが立ち上がる」
久しぶりの晴天で、 暖かな陽差しが室内にめいっぱい差し込む休日の朝。面倒でずるずると後回しにしていた襖の取り付けに、突如パチンとスイッチが入った。
我が家は、コンクリートに覆われた5階建て、築40年の古団地。南に面したリビングとキッチン、和室、そして北に面した和室の2LDKだ。
春から秋にかけ、リビングと北の部屋を隔てる襖を取り払ってしまう。明るく広々とした1室が出来上がり、涼しい風が流れ込んでくる北の和室にベッドを置いて寝起きする。
しかし、11月も下旬に差し掛かれば、北の部屋は、冷え冷えとした冷蔵庫へと変わり果ててしまう。
冷蔵庫の中で、 心安らかな安眠ができようか?
否――。
日本家屋は優秀である。襖の取り付け、取り外しで、自由に部屋を分断したり、拡張したりできるのだから。
そこで、我が家は冷蔵庫と化した北の部屋にふたをして、冬の間、リビングの暖気を死守することとなる。 そして、私は引越し業者のごとく、北から南の和室へベッドの移動を図るのだ。こんな面倒なことを、もう何年も続けている。
押入れの奥にしまってある襖を取り出すには、当然手前にしまってあるものを全て取り出さなければならない。つまり、襖の出し入れをする度に、これまた面倒な押入れの整理というものが、もれなく特典としてついてくるのだ。
出てくる出てくる。よくぞここまで集めたものだと我ながら感心するほどの、大量の空き瓶とボトル、手作りして保存した多種多様なジャム、和洋製菓材料の数々が――。
その中から、クローブ(丁子)が詰まった袋が出てきた。
何年前のことだろう。
きっかけが何なのか全く覚えていないが、フルーツポマンダーを作ろうと、500グラム入りの業務用クローブを買った。
フルーツポマンダーとは、柑橘やりんごなどの表皮に、スパイスのクローブを挿し込んだ香り玉のこと。ミイラ作りの原理と同じで、防腐作用のあるクローブを果物に挿し込むことで腐敗を防ぐようだ。西洋ではリボンなどで飾り付けをして、冬の室内を彩る装飾にされている。
黄色い柑橘の表面を、茶色いクローブが覆い尽くし、華やかなリボンをあしらう――。
しかし、何を間違えたのか、クローブはわたしの想いと記憶をミイラにしてしまい、押入れの暗闇の中で、忘れ去られたままとなっていた。
晴天の冬空の下、再び光に晒された記憶のミイラは、深い眠りから目覚め、からだを起こして動き出した。わたしは鞄の中に、カボスを一つ、そしてクローブの袋を入れ、実家へ出かけた。
畑で収穫したツミナを分けてほしいと、父親にお願いしていた。
かごの中に無造作に放り込んである大量のツミナを拾い上げてゆくと、柑橘が一つコロンと転がっている。デコポンのように頭が飛び出て、皮は分厚く、手の平に収まる、小ぶりだが美味しくなさそうな柑橘。
「フルーツポマンダーの土台に最適じゃない?!」わたしは、心の中で絶叫した。
この不明柑橘は、畑に生っていた劣等生みかんで、実家のフルーツかごに何個か盛られている。記憶のミイラとなって押入れの中で眠っていたフルーツポマンダーは、ほんの数時間前に目覚めたばかりだというのに、手足を伸ばしてわたしの先へ先へとぐんぐん進んでゆく。
わたしは、少し怖くなった。もはや、わたしの意志ではなく、フルーツポマンダーの意志が、何ものかを動かしているということに――。
母親が水彩画で使用しているマスキングテープを借り、後でリボンを飾るため、みかんの表皮に十文字にテープを貼る。マスキングテープを貼っていない表皮に、竹串でしっかりと穴を作り、クローブを隙間無く挿し込んでゆく。
手元からみかんとクローブの香りが立ち上がり、気持ちがゆるゆると解けてゆく。
点としてのクローブを、面としての柑橘に挿し込んでゆくと言う、極めて地味で単調な手作業が、心と精神の動きを減速させ、やがて忘我の状態へ導いてゆく。何という癒しだろう。
クリスマスまでの短い期間、フルーツポマンダーを室内装飾として楽しむのであれば、腐敗を防ぐために、執拗にクローブを全面に施す必要はないだろう。
むしろ、球体を覆う面に、点としてのクローブをどのように施すか、幾何学的デザインに工夫を凝らすことのほうが、ずっと楽しいに違いない。
頭と心、そして冬の長い夜の時間に、安息と喜びのスパイスを利かせて。
2019年12月2日
「鉄骨造とIKEAキッチン」

 岐阜県羽島市の「羽島の家」。設計は上原設計さんの鉄骨造ですが、ようやく完成が見えてきました。
岐阜県羽島市の「羽島の家」。設計は上原設計さんの鉄骨造ですが、ようやく完成が見えてきました。現在、鉄骨接合部で使うハイテンションボルトの数が国家レベルで不足してます。最近は少し生産が増えて需要が減り改善されている模様ですが、オリンピック特需や消費税の駆け込み需要、職人不足などが原因と思われます。弊社も多分に漏れず、ハイテンションボルトの調達不足により当初設計段階の設定工期から2ヶ月遅れました。

 先日のコラムでご紹介した「楽田の家」もIKEAキッチンでしたが、こちらもIKEAキッチンです。後日また完成した画像をアップしたいと思ってます。
先日のコラムでご紹介した「楽田の家」もIKEAキッチンでしたが、こちらもIKEAキッチンです。後日また完成した画像をアップしたいと思ってます。鉄骨造もなかなか面白かったなぁ…。ただ、木造とは職人さんや業者の質感?(笑)が少し違う…。
2019年11月27日
「キャロットケーキが落っこちてきた」
走り書きした幾つもの小さな紙切れが、頭の引き出しの中にくちゃくちゃになって仕舞い込んである。この引き出し、建てつけが悪く、引こうとするとガタガタ音をたて、中の物が思うように取り出せない。引き出しの奥に入ったまま忘れ去られる紙切れもあれば、何かの拍子に、引き出しの暗闇から突然、光の元へ取り出される運のよい紙切れもある。
キャロットケーキは、そんな運の良い紙切れのひとつであった。
キャロットケーキというものを知ったのは、焼き菓子のレシピを貪り読んでいた7年ほど前だろうか。イギリスのクラシックケーキばかりを集めた本があり、そこで初めてキャロットケーキという存在を知ったのだと思う。
頭の中で想像してみる、キャロットケーキの味。
美味しいのか、不味いのか、まったく分からない未知の領域――。
いつか作るだろうと走り書きした紙切れは、頭の引き出しの奥に放り込まれ、時は流れた。
先月から、焼き菓子のレパートリーを広げて、色々と試作を続けている。
図書館で製菓の本を何冊も借りて目を通していると、あちこちからキャロットケーキが姿を現した。
その時、頭の中のがたついた引き出しから、古ぼけた紙切れが1枚、音をたてて眼前へと落っこちてきた。
忘れ去られていた紙切れを、幸運にも手のひらに握り締めたのはいいけれど、肝心のキャロットケーキの味がまるで想像できないのは、依然として変わらない。
紙切れは北風に吹かれ、手の届かない遠い彼方へ消えていってしまうのだろうか――。
名古屋駅へ、いつものように製菓材料を仕入れに行く。
隣接する高級食料品店を冷やかしていると、ショーケースに某店のキャロットケーキが鎮座している。キャロットケーキは、決して粋な外見ではない。むしろ野暮ったくて、親しみのわく姿をしている。
ここで出会ったのも何かの縁だ。いや、必然の出会いに違いない。
分厚いチーズフローティングをどっしりと乗せた、無骨な風貌のキャロットケーキを買って食べてみた。
ひと口食べて、気持ちが一気に沈んでしまった。
味も素っ気もない、まったく美味しくないケーキ。これでは、これからわたしが取り組もうとするするキャロットケーキの基準にすらならない。
しかし、お陰で大切なことがはっきりとした。これよりもずっと美味しいキャロットケーキを、自分の手で作りだせばいいのだということを。
怒りというものは、時に素晴らしいスタートを約束するもののようだ。
わたしの情熱の炎は、いま最高超に燃え盛っている。
手元に、キャロットケーキのレシピが幾つもある。使用する素材の基本形は皆同じだが、どれも配合が大きく異なる。
嗅覚を利かせて、そのうちのひとつに、アレンジを加えて試作をしてみよう。
「パウンド型2台分」
・生で食べても美味しい、堅くない人参(皮付きのまますりおろす)250グラム
・卵 170グラム
・粗糖 130グラム
・黒糖 30グラム
・米油(無味無臭の油なら何でもいい)210グラム
・中力粉 170グラム
・全粒粉 30グラム
・ベーキングパウダー 小さじ2
・重曹 小さじ1
・シナモンとナツメグのパウダー、カトルエピス(パウンドケーキ作りには欠かせない、わたしの必須スパイス。これを入れるだけで、ケーキの味の世界が広がる)各小さじ1
・塩 一つまみ
・160度のオーブンで5〜10分乾煎りしたクルミを砕いたもの 80グラム
・ラム酒漬けレーズン(冬の間、いつでも焼き菓子が作れるように、ラム酒にオイルコーティングしていないレーズンを漬け込んでおく)60グラム
1.卵、砂糖、油をボールに入れ、ハンドミキサーでもったりと白っぽくなるまで混ぜる。
2.人参、クルミ、レーズンを加えて、ゴムベラで全体を混ぜる。
3.粉類をすべてふるいにかけて加える。ゴムベラで、生地全体を切るようにして、粉気がなくなるまで、しっかりと混ぜる。
4.クッキングシートを敷いたパウンド型に、生地を8分目まで入れ、200度で余熱したオーブンに入れ、180度で30分ほど焼く。
5.黒々と美しく膨らんだキャロットケーキ。焼きあがったら型から外し、網の上で荒熱を取る。
「ケーキの仕上げにかけるフローティング」(フローティングがなくても、充分に美味しい)
・クリームチーズ 200グラム
・バター 10グラム
・粉砂糖 20グラム
1.ボールにクリームチーズを入れてゴムベラでならし、常温で柔らかくしておいたバターを2回ほどに分けて加え、全体が滑らかになるように混ぜる。
2.粉砂糖をふるい入れ、全体をよく混ぜ合わせる。
3.荒熱が取れたキャロットケーキの上部に、均一の厚みになるよう塗り広げる。
4.ケーキ全体をラップで包み、手でフローティングの形を整える。
・生で食べても美味しい、堅くない人参(皮付きのまますりおろす)250グラム
・卵 170グラム
・粗糖 130グラム
・黒糖 30グラム
・米油(無味無臭の油なら何でもいい)210グラム
・中力粉 170グラム
・全粒粉 30グラム
・ベーキングパウダー 小さじ2
・重曹 小さじ1
・シナモンとナツメグのパウダー、カトルエピス(パウンドケーキ作りには欠かせない、わたしの必須スパイス。これを入れるだけで、ケーキの味の世界が広がる)各小さじ1
・塩 一つまみ
・160度のオーブンで5〜10分乾煎りしたクルミを砕いたもの 80グラム
・ラム酒漬けレーズン(冬の間、いつでも焼き菓子が作れるように、ラム酒にオイルコーティングしていないレーズンを漬け込んでおく)60グラム
1.卵、砂糖、油をボールに入れ、ハンドミキサーでもったりと白っぽくなるまで混ぜる。
2.人参、クルミ、レーズンを加えて、ゴムベラで全体を混ぜる。
3.粉類をすべてふるいにかけて加える。ゴムベラで、生地全体を切るようにして、粉気がなくなるまで、しっかりと混ぜる。
4.クッキングシートを敷いたパウンド型に、生地を8分目まで入れ、200度で余熱したオーブンに入れ、180度で30分ほど焼く。
5.黒々と美しく膨らんだキャロットケーキ。焼きあがったら型から外し、網の上で荒熱を取る。
「ケーキの仕上げにかけるフローティング」(フローティングがなくても、充分に美味しい)
・クリームチーズ 200グラム
・バター 10グラム
・粉砂糖 20グラム
1.ボールにクリームチーズを入れてゴムベラでならし、常温で柔らかくしておいたバターを2回ほどに分けて加え、全体が滑らかになるように混ぜる。
2.粉砂糖をふるい入れ、全体をよく混ぜ合わせる。
3.荒熱が取れたキャロットケーキの上部に、均一の厚みになるよう塗り広げる。
4.ケーキ全体をラップで包み、手でフローティングの形を整える。
キャロットケーキで大切なことは、クルミの量をケチったりせずに、たっぷりと入れること。しっとりとした生地の中に、歯ごたえのあるクルミがゴロゴロと入っている。このバランスこそが、キャロットケーキをキャロットケーキたらしめていると断言してもいい。
今回作ったキャロットケーキは、スパイスと黒糖が見事に調和し、何とも言えない魅力を醸し出している。
スパイスと砂糖を何種類かキッチンに揃えておくと、焼き菓子作りの発想と、味の自由が格段に広がる。人参とスパイス、黒糖が三者三様に手をつなぎ、まったく新たな味へと昇華した、美味しいキャロットケーキの出来上がり。
家庭でつくるお菓子は、わがままが効く、最も贅沢なもの。
嫌いなものは入れなくていいし、好きなものは好きなだけ入れればいい。素材は厳選できるし、酸いも甘いも、好きなように調整できる、世界にたった一つの、お菓子のオーダーメイド。
この冬、時間と財布、エネルギーの許す限り、焼き菓子の深い森の中を、迷いながらも手探りしながら進んでゆきたい。
2019年11月25日
「造るのは生き方」
家造りの相談を何件も経験させてもらっていると、様々な事柄に出逢います。例えば夫婦のこと、親子のこと、親戚のこと、近隣のこと…全て人間関係での事柄。設計終盤で延期になったことも、途中で頓挫したことも、こちらが中止を提案したこともありました。この世の現象は心に起因し、心によって展開されます。相手を想い優しい心が因子となれば、気持ちのよい結果が現れる。僕は現実からも大好きな仏教からも、この事を痛感して学んでいます。
家をあーだこーだするよりも、重要な根幹となる避けては通れない様々な人間関係の問題が、どの家造りでもまずありますよね。
 考えて、苦心して産み出したデザインの小箱は、お蔵入りになることもたまにはあります。産んだからには最後まで造りあげたい。それは親心。
考えて、苦心して産み出したデザインの小箱は、お蔵入りになることもたまにはあります。産んだからには最後まで造りあげたい。それは親心。その気持ちは強いですが表に出さず、僕は現実から目をそらさず飄々と流れのままに漂うだけ。
全てはきっと時間が解決してくれます。心をプラスに。良いことだけをイメージして。
2019年11月21日
「わたしを買う」
「物買ってくる。自分買ってくる。」。陶芸家、河井寛次郎(1890−1966年)が残した言葉に触れて、思わずどきりとする。
安いものであれ何であれ、わたしが選び、手に入れたもの。それは、自分を投影するもの、自分自身そのものであるということは、心の片隅では気がついていた。
だからこそ、安いものを選ぶ時は、余程気をつけなければならないということも。
値段が問題なのではなく、自分の目と心、価値、美意識が、そこにちゃんと据えられているかどうかが問題なのだ。
数週間前のこと。
近所のスーパーの店頭で、月1回行われるバザーに足を運んだ。
以前、がらくた山から掘り出し物を手に入れたので、今回もわずかな期待をもって出かけたのであった。
ここは、「中高年が意を決した断捨離」が、最終的に流れ着いた場所。
長い年月、押入れの中で眠らせていた食器類を、惜しいけれどもとうとう手放した、という品々が雑多に並んでいるのだ。
さて、いったいどんな掘り出し物があるだろう?
実験室においてある標本瓶のような、巨大な蓋付きのガラス容器が、目に飛びこんできた。
ヒマワリなどを豪快に生ける大きな花瓶を、もう何年も欲しいと思っていたが、このガラス容器、欲しいと思っていた材質と大きさ、まさにそのものだ。
善意のみで支えられているバザー。安値で手に入れられることは、経験上よく分かっている。
しかし、このガラス容器にいたってはどうだろう?
取るに足らない心配は、150円という破格の値段によってたちまち霧散し、わたしは繊細なガラス容器を、いとも容易に手に入れてしまったのであった。
大きな荷物を抱えて帰宅したものの、目下、ダイナミックに生ける花というものがない。
仕方なく、陽のあたる窓辺の棚に、飾り物として置いてみる。
そして、その姿を眺めつづけて数週間、この買い物は間違っていたのではないだろうか、という不安がよぎり始めた。
職場の畑で、コスモスが満開となった。
薄いピンクや白いもの、赤く深みのある花。異なる色のコスモスが、好き勝手にあちらこちらに顔を向け、快活そのものに咲いている。
手持ち無沙汰で、ただじーっとしていた大きなガラス容器の出番が、とうとうやって来た。
20本ほどのコスモスを選りすぐって切り、一晩水揚げをする。
水を充分に吸い上げて生き生きとしているコスモスを、60センチほどの長さに切り揃え、くだんのガラス容器に1本ずつ生けてゆく。
野放図に咲き誇っていた野良娘のようなコスモスは、澄んだ湖を湛えるガラス容器の中で、洗練された乙女へと、見事に生まれ変わった。
この買い物に、間違いはなかった――。
「物買ってくる。自分買ってくる」。
自分自身を投影するものであると同時に、自分のライフスタイル、自分の未来の時間を買っているのだと思うと、鏡で自分の姿を見るよりも、買って手に入れたものを見つめることのほうが、より現実的で、より恐ろしいことではないだろうか。
2019年11月14日
「大事なもの」
昨年からずーっと忙しい。一人で全てをこなすということは斯くも大変なことなのか…。接客、デザイン、設計、製図、申請、積算、施工、入札、打ち合わせ、修繕、アフターフォロー…これに日常の子育てと生活が入ってくると、もはや毎日をこなすだけで精一杯の人生が展開されていく。それもあって今年SNSを辞めた。Facebookとブログ…元々インスタはやっていない。そのため、この「あおけんコラム」が唯一の表現場所になった。しかし、それもなかなか自分では更新できず、友人の麻衣子さんにお願いしている。麻衣子さんの文章や生き方に魅せられている私は、毎回更新を楽しみにしている。
家づくりの情報は巷に最早沢山溢れている。弊社が更新しなくてもゴロゴロその辺にある。情報を求めて弊社のホームページを訪れる方にとっては困惑するかもしれない。けれど、それでいいのだ…。
彼女のコラムには生き方の大切な根幹が溢れている。前回のワインの更新もしかり。ワインの味を手間と時間を加えてデザインする彼女のような姿勢は、家づくりをする人間にとって最も参考にすべきこと。依存するのではなく、自ら設計する人間と共に工夫する姿勢こそ最後に素敵なお家になりうる可能性を秘める。
「麻衣子さんのコラムを受け止めていただける思想のクライアントと家づくりがしてみたい!!」…そう思って、私は彼女にコラムの更新を依頼し続けている。 (彼女の方が「コラム続けても意味ないんじゃない?」と心配してくれている。)
 もうすぐ1件のお家が完成する。コストを抑えるために構造材を露出させ、床は床暖房を入れた土間、外壁にはフレキシブルボード…コストを抑える内容だが、逃げる納まりが一切出来ないことで手間はコストと反比例して増した。納まりの思考も難しかった…。
もうすぐ1件のお家が完成する。コストを抑えるために構造材を露出させ、床は床暖房を入れた土間、外壁にはフレキシブルボード…コストを抑える内容だが、逃げる納まりが一切出来ないことで手間はコストと反比例して増した。納まりの思考も難しかった…。けれど僕自身また設計の幅が広がるような経験をした。何事もマイナスに考えず、感謝してありがたく受け止めたい。
2019年11月12日
「暖炉の炎をグラスに満たして」
夜の冷え込みが忍び寄って来た。お風呂に入り寝るまでの間、暖炉の炎のように、心とからだを温めてくれる飲み物。
それは、真っ赤なグリューワイン。
ぶどう酒に、香辛料などを加えて温めたものが、ドイツ語でグリューワイン。これがフランス語になると、ヴァン・ショー、英語だとマルド・ワイン。
日本語で言うホットワインは陳腐な響きで嫌なので、わたしはグリューワイン、もしくはヴァン・ショーと呼びたい。
音の響きからして、すでに気分が高揚してくる。
さて、美味しいグリューワインを作るにはどうしたらいいだろう?
ソムリエとして働いていた職場の同僚に、お手軽なワインでどんなものが向いているだろうかと尋ねてみた。
「チリ産の赤ワインは、安くて品質も安定しているから、一度試してみてはどうだろうか。500円のものも、1000円のものも、味に大きな違いはないですよ」。
ということで、近所のスーパーで、チリ産ワインを物色してみる。
軽い味わいよりも、深みのある味わいのほうが、グリューワインには向いていそうなので、500円程度のチリ産ワインで、ミディアム・ボディーの「カベルネ・ソーヴィニヨン/シラー」を買ってみる。
これ、ワインとして飲むと、「渋い」のひと言。
この堅物なワインがグリューワインとなって、いったいどのような味の変化を遂げるというのか?
なんせ、冷え込む初冬の夜。
夜の暗さと、時間はたっぷりとある。編み物を編むように、楽しみながらグリューワインをデザインしてみよう。
300ミリリットルほどの赤ワインを、アルミ以外の耐酸性の鍋に入れる。
我が家には、丁度グリューワインと申し合わせたように、果物が揃っているので、そこから姫りんご2個と小ぶりなみかん1個、小さな甘柿1個、そして手の指の爪ほどの大きさの生姜を、それそれ厚めにスライスする。
シナモンスティック1/3本、スダチの絞り汁大さじ1、蜂蜜大さじ1杯、これらをすべて鍋の中に入れる。沸騰しないように、極弱火で全体の味がまろやかになるまで、そのまま火にかけておく。
最初は赤ワインの渋味が前面に出て雑味が強いが、1時間ほど経つと渋みの角が取れ、非常に奥深い味わいへと変化する。
果物の酸味と甘み、蜂蜜の甘み、スパイスの香りが見事に融和し、ふくよかで濃厚な味わいとなる。
一度にたくさん仕込んでおき、冷めたら果物とスパイスを入れたまま、グリューワインをガラス容器に入れて冷蔵保存する。
翌日の味は、さらに味わい深い。天上の花園から滴り落ちた雫とでもいったらいいだろうか――。
今回は、家にあった果物を使用したが、酸味の強いキウイや、甘みの深いベリー系の果物、熱帯系の華やかな香りを持つ果物を加えたら、グリューワインはまったく異なる花々を咲かせるのだろう。
果実の代わりに、使いかけのジャムを使ってみてもいいかもしれない。
我が心と舌にのみ広がる未知の花園を、冬の間グリューワインの中に探し求める喜び。
ムートンのかかった籐椅子にからだを沈め、静かな夜の時間と、一日の終わりを、グリューワインとともにゆっくり飲み込んでゆく。心とからだが、夜の世界にじわじわと溶け込んで行く。
これで、暖炉の炎があれば、もう言うことはない。
2019年11月6日
「三種の神器」
夕食を食べ終え、台所の後片付けをする。実家の母は、台所用の可燃ゴミ袋を新しいものに取り替え、一日続いた仕事の幕を閉じる。
わたしはシンクと排水口を洗った後、布巾と台布巾、手拭きを、湯を張った中型のステンレス鍋へ放り込み、粉石けんと酸素系漂白剤を入れて煮沸洗いをする。
食器を洗う不織布と、まな板を洗う束子も、別の小さなステンレス鍋で同じように煮沸する。
やれやれ、これで今日も台所仕事が終わった――。
台所で使った布巾をバケツに溜め置き、一日を終えると鍋で煮沸洗いをする。
20代の頃、女優で随筆家の沢村貞子(1908〜1996年)の本を読んでから、わたしも彼女を見習い、毎晩煮沸洗浄をするようになった。
今までこの習慣が続いているのは、台所で使う布巾類が、洗濯物の中で最も汚れがひどく、しかも最も清潔を保たなければならない物だからだ。
コンロの汚れや、カレー、しょう油などの染みでひどく汚れてしまった台布巾も、煮沸漂白してしまえば、もとの真っ白な布巾へと見事に生まれ変わる。
この様な台布巾の汚れと、衣類の汚れの質は、根本的に異なるので、洗濯機に何でもかんでも放り込んでしまったところで、汚れが落ちているのか、それとも拡散しているのか分かったものではない。
ちなみに、洗面所や入浴後の白いタオルも、使った後に専用バケツに入れ、酸素系漂白剤と熱湯を入れたまま一晩漬け置き、他の洗濯物と一緒に洗濯機にかける。
酸素系漂白剤は、白さと日常の中心軸を保つ上で、もはやわたしにはなくてはならない、生活のメインツール、最強の相棒となっている。
わたしは敏感肌なので、添加剤の多い洗剤を使うと、とたんに肌に痒みが出てしまう。
そこで、食器は、米ぬか石鹸を不織布で泡立てて洗い、洗濯は粉石鹸を使い、すすぎにクエン酸を加える。柔軟剤と同じ役割だが、人工的な強い香りや、無駄なものが添加されていないので、わたしはこちらの方が大歓迎だ。
粉石鹸、酸素系漂白剤に併せて、クエン酸が、我が家の清潔と肌の安全を保つ、三種の神器となっている。
真っ白な布巾やタオルが常にあるということ。それはとても気持ちの良いものだ。
生活というものは、自ら生み出した汚れを、繰り返し繰り返し拭っていく行為なのだなあと、白いタオルを干す度に、しみじみ思うのである。
2019年10月31日
「語り部としての音楽」
10月上旬。44歳の誕生日プレゼントとして、母親と念願のサラ・チャン(米、1980年生まれ)のヴァイオリン・リサイタルに行ってきた。数年前のこと。ブルッフのヴァイオリン協奏曲を、NHK交響楽団と協演する彼女をインターネット上で見てからというもの、この女性の演奏を直に聴いてみたいという強い想いがあった。
2008年当時の姿は、他を寄せ付けない、まるで女王様のような雰囲気と妖艶さ、そして得体の知れない爆発力と強さが満ち溢れていた。
この女性が放つエネルギーは、一体何なのだろう? 大きな期待をもって、わたしは出かけて行ったのであった。
鋭い棘を身につけた真紅のバラが、その香りをあたり一面に解き放ち、自信満々に咲き誇っている――。そんなコンサートになるのだろうと思っていた。
しかしどうしたことだろう。この真紅のバラには棘が一切見当たらず、しかも蕾を開ききらずに、その香りを奥へ奥へと、秘め事のように用心深く潜めている。
眼を閉じて触れるサラ・チャンの奏でる音には、棘のようにツンと澄ました過剰や誇張というものが何ひとつなく、音楽に誠実であろうとする一心さと、迷いのなさが、そのままヴァイオリンから音色となって清く澱みなく流れ出る。
わたしは何故だろう、そこに古今東西に生きる女達の誇り高き姿を見た。
「女として生きることの強い意志」が、サラ・チャンの奏でるヴァイオリンを通して、次から次へと泉のように溢れ出てくるのだ。
ある女は深い森の中を飛び回り、ある女は星と戯れ、またある女は街中を踊り抜ける。
彼女たちは、なんと誇らしげに嘘偽りなく、堂々と強く美しく生きているのだろう。
眼を閉じた世界に現われる彼女たちは、サラ・チャンのヴァイオリンから解き放たれた、現代のヴィーナス、まさにそのものだ。
サラ・チャンは、この世に生きる女たちの語り部となって、ヴァイオリンを声に、彼女たちの命を歌いあげる。
かつてインターネット上で観た、彼女の放つエネルギーというもの。
それは、わたしの期待を大きく裏切り、まったく想像もしなかった、別次元のものへと大きく変容したようだ。
静かな湖面を荒らすことなく、風がふっと吹き抜ける。うっすらと、真紅のバラの香りを残して。
プログラム
バルトーク・ベーラ:ルーマニア民族舞曲
セザール・フランク:ヴァイオリン・ソナタ イ長調
エドワード・エルガー:愛の挨拶
アントニオ・バッジーニ:妖精の踊り
アントニン・ドヴォルザーク:ロマンス ヘ短調
モーリス・ラヴェル:ツィガーヌ
バルトーク・ベーラ:ルーマニア民族舞曲
セザール・フランク:ヴァイオリン・ソナタ イ長調
エドワード・エルガー:愛の挨拶
アントニオ・バッジーニ:妖精の踊り
アントニン・ドヴォルザーク:ロマンス ヘ短調
モーリス・ラヴェル:ツィガーヌ
2019年10月23日
「危険な味」
およそ3キロの利平栗が、今年も岐阜の親戚から実家へ送られてきた。毎年渋皮煮にしてみるのだけれども、どうもこの栗は食感の柔らかさという点で劣る。
そこで、大きな鍋で大量の栗を蒸して、濾す。
濾した栗の食感は滑らかになり、濃厚な旨みだけがしっかりと口に残る。
この旨みの詰まった濾し栗から、栗きんとんと栗ジャムに展開することができる。
台風で仕事が休みとなった日。
スーパーは半日の営業。レンタルビデオ店に行けば、家族連れでごったがえしている。
家に閉じこもって、各々の楽しみを満喫するには絶好の日ではないか。
それならばと、わたしは家で静かに栗仕事をすることに決めた。
まず、洗った栗を、約50分ほど蒸し器で蒸す。荒熱が取れたら、包丁で半分に切り、小さいスプーンで中の実をこそげ取る。
実に根気のいる作業だが、始めてしまったら後には引けない。ここは腹をくくり、「ものごとには、必ず終わりがある」と心の中で唱えながら、気長に行う。
こそげ取った実を、目の細かいザルで濾す。
ここまで仕上げれば、冷凍保存して、時間があるときに栗きんとんや栗ジャムを作ることができる。
栗きんとんは、濾した栗の重量の20パーセントの上白糖を混ぜ、ラップをしないで電子レンジに30秒ほどかける。
栗と砂糖がしっかりと馴染むように、ひたすら練る。練るつづけると、やがて全体がしっとりとまとまってくる。
これを手のひらで団子に軽くまとめ、ガーゼや晒しに包んで、しっかりと締める。
これで、栗きんとんはできあがり。和三盆があれば、上白糖よりも上品な味で、口解けのよい栗きんとんが仕上がるだろう。
土台の濾し栗さえ作ってしまえば、栗きんとんは、思ったよりも簡単に作れてしまうのだ。
さて、ここからは栗ジャムを展開してゆこう。
わたしは、栗きんとんよりも、この栗ジャムの方がよっぽど好きだ。
栗の美味さがぎゅーっと凝縮した味は、幸福の味、まさにそのもの。昨晩など、疲れ果てていることを口実に、冷蔵庫から小さなひと瓶を取り出し、立ったままスプーンですくって、またたく間に完食してしまった。つまり、それくらい舌を虜にさせる、とびきり危険な味なのだ。
作った分量を記してみる。
濾した栗516グラム、グラニュー糖310グラム、ひとつまみの塩、水300ミリリットル、ラム酒小さじ1。
鍋に栗と水を入れ、中火で少し煮る。
栗と水が馴染んだら、グラニュー糖と塩を入れ、弱めの中火でひたすら木べらでかきまぜながら、水分を飛ばしてゆく。
常にかき混ぜていないと、熱々のジャムがマグマのように鍋から噴きだしてくるので、注意が必要だ。忍耐強くかき混ぜ続けていると、全体の色が、薄い茶色から濃い茶色へと変化してゆく。
頻繁に味見をしてみよう。栗の味わいに深みが出てきて、砂糖の甘みと交わってゆくのが分かる。
15分から20分ほど経ち、あんこのようにぼてっとしてきたら、ラム酒を加えてアルコールを飛ばす。ジャムの適度な粘度が分からないようなら、小皿にジャムを少し取り置き、しばらく冷蔵庫に入れておく。冷えたジャムがまだ緩いようだったら、再び火を通せばいい。
煮沸消毒した瓶に、ジャムが熱いうちに充填し、ふたをしかりと閉める。
常温で長期保存するために、ここで脱気処理をしてみよう。
鍋底にふきんを敷き、熱い瓶を互いに触れ合わないように置き、40度位の湯を8分目くらいまで注ぎ、強火にかける。
15分ほど沸騰させて火を止め、冷めるまでそのままにしておく。
湯が冷めたら瓶を取り出し、常温でひと晩置いておく。
翌朝、ふたがぺこんとへこんでいたら、瓶内の空気が完全に脱気した証拠。
今回の分量で、150ミリリットルの瓶、5本分が出来上がった。
栗ジャムは、牛乳を足し、再び火にかけて水分を飛ばすと、マロンペーストとなる。
これで、モンブランを作ったり、パウンドケーキに混ぜ込んだりできるので、たくさん作って瓶詰め保存しておくと、とても重宝する。
このコラムを書いていたら、無性に甘いものが食べたくなってきた。
クッキーもビスケットもない。そこで、冷蔵庫の扉を開け、栗のジャムをまたひと瓶、またたく間に平らげてしまった。
ああ、これでは、モンブランを作る前に、栗ジャムの底が尽いてしまう――。
2019年10月16日
「真っ赤なスープを召し上がれ」
10月に入って暑さが落ち着き、記憶から遠ざかっていた涼しさというものが、思わせぶりに肌をかすめる。すると、からだのどこかで深い眠りについていた「食欲」が突如として目を覚ました。夕食も終わった、夜7時過ぎ。
野菜がたっぷりと入ったミネストローネを、無性に作りたくなった。
冷蔵庫の中をのぞけば、人参とキャベツがある。
食品棚には、小さな玉ねぎと、小ぶりなじゃがいも、初夏に買いだめして干しておいたニンニクがごろごろとしている。
冷凍庫を開けると、スライスして少し干した椎茸と、千切りにしておいたハムが、霜をうっすらまとってカチカチに凍りついている。
あとは、いつでもミネストローネが作れるように買っておいたカゴメのトマトジュースひと缶が、微動だにせず、じっと出番を待ちつづけている。
窓から入り込むうっすら冷たい秋の夜気に包まれながら、静かな音楽を奏でるように、真っ赤なミネストローネを作りはじめる。
ミネストローネというと、野菜を几帳面に、小さなサイコロ状に切りそろえてることが「美徳」であると、固く信じていた時期がある。
火の通りが均一になるから?口に入れた時の具合がいいから?見た目が美しいから?
わたしには、分からない。でも、そんなことに神経とエネルギーを使って、ミネストローネ作りに疲れ果てるのはばかばかしい。
スープは調理が簡単で、滋養が豊富で、温かいのが信条であるから、もっと大らかな気持ちで作ってもいいのではないだろうか。
自分に都合のいい解釈をして、人参、玉ねぎ、じゃがいもを、1.5センチくらいのサイズに、ザクザクと切ってゆく。あくまでも、ザクザクと。キャベツも同じように、ザクザクと切る。
さて、ここで登場するのが、OXO(オクソー)製ノンスティック・コーティング、直径18センチのソースパン。
フォルムの美しさと、重量感にひと目ぼれし、バーゲンで衝動買いをした鍋だ。
米油を敷いた鍋に、キャベツ以外の材料をすべて放り込み、野菜全体に満遍なく油が回るように、弱火で軽く炒めてゆく。
鍋底から鍋縁までの絶妙な傾斜と深さで、ゴロゴロとしている野菜たちを木べらで炒めてゆく動作に、いちいち「イラッ」とすることが一切ない。
抜群の包容力と安定感、そして滑らかさ。
この鍋でスープを作ると、なぜか心が落ち着き、料理するワクワク感に満たされる。
イライラしないということ――。
穏やかで、美味しい料理を仕上げる上で、これよりも重要なことってあるだろうか?
体の動きにスムーズに寄り添う道具というものは、料理の腕、まさにそのものだ。
全体に油がまわったら、塩を振り、食塩不使用のトマトジュースと、その3倍ほどの水、コンソメ顆粒、キャベツを加え、ふたをして弱火で2時間以上煮込む。
ここで、小さじ1杯以上を入れると、ぐっと味に深みが出るのが乾燥セロリの葉。
生のセロリの葉を天日で完全に乾燥させ、パリパリになったら細かくして瓶に詰めておく。
カレーやスープに旨みを加える、重宝するハーブだ。
ところで、2時間以上も煮込まないとだめ?という声が聞こえてきそうだ。
30分、1時間、2時間後と、その都度スープの味をみてみれば、すぐさま納得するにちがいない。
1時間ほどでは、トマトの酸味は消えず、野菜の甘みも充分ににじみ出ず、全体の味わいがきつい。
それが、2時間以上煮ていると、野菜の甘みと旨みがぐっと増し、トマトの酸味も影を潜め、とても穏やかな味わいに成長する。
3時間も煮たら、ジャガイモも玉ねぎも、かつての姿をなくして、スープの中へ溶け込んでしまう。こうなると、先述の、「野菜は細かく、サイコロ状に切りそろえるべし」という台詞が、3時間後には、すでに意味をなさなくなっていることがお分かりになるだろう。
OXOの鍋ぶたは密閉性が抜群なので、鍋の蒸気を外へ逃がさず、旨みはさらに充填される。
夜10時半。
歯も磨き、ベッドに潜り込むだけのわたしは、なぜか空腹に満ち満ちている。
出来立てのミネストローネを、真っ白なカップに注いで、「ほんの味見程度ね」と口にする。
温かさと、美味さと、滋養に包まれた真っ赤なスープは、たちまち食欲に火をつけた。
長い眠りからようやく目覚めた食欲を押さえつけることは、私にはもはや不可能だ。
白いカップに何度も真っ赤なスープが注がれたころ、胃の中で騒がしく暴れていた食欲も、ようやく満足して大人しくなった。
心とからだに満々と真っ赤なスープを湛え、わたしは真っ黒な眠りの闇へと、安心して沈んでいくのであった。
2019年10月8日
「ごみ捨ての美学」
月2回の紙ごみ収集日。団地のゴミ捨て場を見て、唖然とする。
新聞、ダンボール以外の紙ごみ(雑がみ)を出している住民が、団地約30世帯のうち、わたしひとりしかいないのだ。
トイレットペーパーの芯や、使い終わったメモ書き、感熱紙でないレシート、衣類などに付いた商品タグ、バンドエイドを包んでいた紙、チラシ、購入した商品の紙製パッケージ――。
生活のなかで廃棄する紙製品は以外に多い。
キッチンの片隅に小さな紙専用のダストボックスを置き、細々と出る紙ごみをそこに放り込む。溜まったら、紙袋に詰め込み、それが一杯になったら収集日に捨てる。
たったそれだけの習慣で、紙ごみの分別は簡単にできてしまう。
実家も団地の住民と同じく、紙ごみはゴミ箱にぽいぽいと捨てて、可燃ごみとして一緒に廃棄している。人の生活に口を挟むのははばかられるので、敢えて何も言いはしないが、長年の習慣を変えることは、他人からどんなに言われても、本人の意識がなければ、なかなか難しいものなのだ。
可燃ごみから紙ごみを取り除くと、廃棄するごみのかさが明らかに減少することに気がつく。
残された可燃ごみの中身は、大半が野菜くず。
わたしに庭があったら、堆肥ボックスの中に放り込んで土に還してしまうが、団地のベランダではどうしようもない。
重量とかさのある野菜くずが家庭内で堆肥化できれば、可燃ごみの量は激減する。そして、堆肥化した土が、庭の果樹を潤し、熟れた果実をわたしたちが口にする。
庭のある多くの家庭が、この循環するシステムを実現したならば! これはわたしの理想の世界だ。
野菜や豆腐、納豆、石鹸、化粧品、雑貨――。
あらゆる製品に、皮膚のごとくまとわりついているプラスチック包装という厄介極まりないごみ。
買い物をして、家で製品をパッケージから取り出したら、プラスチック包装を神社のおみくじのように、ひも状にしてから結び、なるべくかさを小さくしてから専用のダストボックスに捨てる。
プラスチックは重量はないが、とにかくかさが張るので、何も考えないでごみ袋に放り込むと、大半は空気を捨てているような無駄な結果となる。
そんなプラスチックごみを捨てるポイントは、マトリョーシカの入れ子方式だ。
以前、公立保育園の給食室で働いていたときのこと。
市の財政にゆとりがないために、月に使用できるごみ袋の枚数が制限されていた。そこで、働く人々は工夫を凝らすのだ。
ごみとして出たポリ袋に、詰めれるだけのごみを詰める。一回り大きなポリ袋が出たらそこに、小さくまとめた先ほどのごみを詰めてゆき、最終的に、大きなごみ専用袋にまとめて排出する。
そこにはどんな隙間も見当たらない、美しくごみの詰まったごみ袋が完成されるのだ。
制約という名のもとで、人はごみの捨て方にまでも美学へと昇華させてしまう知恵があるのか、とつくづく関心し、みずからの生活にも取り入れるようになった。
プラスチックごみも同様で、大きなごみ袋を買わなくても、マトリョーシカのように、ごみの中にごみを詰めてゆく入れ子方式を活用すれば、小さなごみ袋でも、充分にごみの排出がまかなえる。
空気を入れない、隙間を作らない、ぱんぱんに詰まった完璧な美しいごみ袋だ。
もちろん、生活に無駄を省いてゆけば、余分なごみの廃棄も減るだろう。
生活の美学というものは、どんなところにも見出そうとおもえば存在するだけに、また気づきと実践の難しいものでもある。
2019年10月1日
「音の気配」
季節は秋へと移り変わろうとし、もはや過去形になりつつある今年の夏。振り返れば、わたしの頭脳は、思考や意思、意欲といったものすべてが仮死状態となり、陽に焙られるまま日干しとなってゆく魚のように、ベッドで仰向けになり、生きる最後の藁をすがるようにして細々と本のページをめくっていた。
しかし幸いにも、ページの中に、作家、森茉莉(もりまり、明治36年生れ)とういう、ひとりの女性の感受性と、明治時代の東京山の手の幻想に出会ったのであった。
日干しの魚は、日干しとなりきらずに、再び息を吹き返したのである。
幼い茉莉を取り囲む、明治の雰囲気は、愛と安心に包まれた生活は、光と、音と、香りとなって、茉莉の心の中に大切にしまわれている。
わたしはその大切な小箱の中を、そっと覗いてみる。
人力車の車夫が、掛け声とともに東京の山の手を駆けてゆく音。
母親の着物から漂う清心丹の香り。
薄いガラス戸を雨が激しく叩きつけ、家中を包み込んでしまう音。
父親の軍服にしみこんだ葉巻の香り。
畳の上にこぼれる、着物の衣擦れの音。
からからと打つ下駄の音。
そして、しんと静まり返った薄暗い室内。
静けさの中にあるからこそ、意味を持つ生活の音、そして香り。
暗闇にともされる、灯火の明りの不規則な揺らぎと余韻、それは闇と光の蜜月のよう。
「『パッパ』。それは、私の心の全部だった。父の胸の中にも、わたしの恋しがる小さな心が、いつでも、温かく包まれて入ってゐた。私の幼い恋と母の心との入ってゐる、懐かしい軍服の胸で、あった」。
あらゆる感覚を呼び覚ますもろもろの気配の中にふわふわと漂いながら、幼い茉莉は、父、森鴎外の愛に包まれた、幸福な時代を過ごすのであった。
そしてその愛さえもが、静寂の中に余韻を残す音、闇にいつまでも揺れる、ほんのりとした明りそのもののようにわたしの目に美しく映るのだ。
今では、夜でも車が走り去る騒音は絶えず、静寂というものが生活から容赦なく奪われてしまった。明かりは煌々と照らされ、闇の深さがどこまでのものか分からないし、明かりの尊さも希薄となりつつある。
わたしたちは、この騒がしさの中で何を耳にし、この明るさの中で何を見つめればいいのだろう。
ものの気配という一種の色気のようなものが、居場所をなくしてどこかへ姿を消してしまった。
わたしは憧憬の眼差しで、森茉莉の「父親の帽子」に綴られた「幼い日々」を眺めるのだ。
生活から生み落された、光と闇、音、香りや雰囲気という、それ自体がまるで意思を持つ、生命ある妖しげな生き物のようなものを――。
東京山の手に響く音を、静寂の上に聞いた森茉莉と、山口県の農村で生まれ育った、明治41年生まれの民俗学者、宮本常一(みやもとつねいち)の記憶の音は、まったく異なるものに違いないが、静寂の上にその音が響いていたということに変わりはないだろう。
宮本が71歳の時に書いた「地の音」(「宮本常一 伝書鳩のように」に収録)は、茉莉が「静かな世界、いろいろの生活の音に囲まれた楽しい世界は、もう私達の手に還ってはこないのだろうか。」と書いてることと、同じことを訴えてるのではないだろうか。
「世の中が静かであったとき、われわれは意味を持つ音を無数に聞くことができたのである。意味をもたない音を騒音といっているが、今日では騒音が意味のある音を消すようになってしまった。
仮に意味があっても自動車や飛行機のたてる音は人間の神経を逆なでする。
そういう音に慣れるということは実はわれわれの感覚の中からいろいろのものを聞きわける能力を失わせているのではないかと思う。
そしてこれでよいのだろうかと思うことが多い。
おそらくもう昔の静かな世界を取り戻すことはできないであろうが、今残っている静かな世界を大切にする対策はたてられないだろうか。
人間にとっては静かに考える場と、静かに聞く場が必要である。
人間をたえず自然の中へ引き戻すことで、人間はいつまでも新しい生命を持ちつづけるのではないだろうか。」
2019年9月25日
「庭という楽園」
広大な庭があったら、さまざまな果樹を植え、育てたい。これはあらゆる意味で、豊かさのへの投資ではないだろうか。
実家の裏にあるお宅は、40坪ほどの庭に、グレープフルーツやみかんなどの柑橘類数種、なつめ、びわ、杏、柿といった果樹を庭いっぱいに育てている。
グレープフルーツの木は、2階の屋根を優に越えて緑を豊かに生い茂らせ、冬になると宝石のような果実をたわわと実らせる。
冬枯れの空の下、常緑の葉と黄金色の果実を眺めるにつけ、目にも幸福を与えてくれる果実の恵みは偉大だなあと、ただただ羨望の眼差しを向けるのである。
そして毎年3月になれば、杏が桃色の花を可憐に咲かせ、樹上は蜜を吸いにやってくる鳥のパラダイスと化す。
果樹と共に暮らすということは、季節が織り成すさまざまな表情に囲まれて暮らすのだということを、借景のおこぼれを授かりながら、しみじみと感じ入るのである。
さて、わたしに庭があったなら?
どうしたって、愛すべきイチヂクを植えたい。
イチヂクは8月から11月まで、次々に実をならす非常に息の長い優良果樹だ。
完熟した果実は皮が薄く、果肉は弾け、蜂蜜のような甘さを満々と湛えている。
咀嚼の必要がまったくない完熟した果実は、口の中で瞬く間に溶け、濃厚な甘みが口内に幸福な余韻をいつまでも残す。
こういう味を覚えてしまうと、スーパーに並ぶイチヂクが食べられなくなってしまうのだ。
完熟したイチヂクは、薄い皮が傷つきやすく輸送には向かない。なので、完熟手前に収穫されたイチヂクが店頭に並ぶこととなる。
これでは、イチヂクの本当の醍醐味を味わうことにはならない。
朝目が覚め、庭を散策し、完熟したイチヂクを木からもぎとり、その場で皮ごとむしゃぶりつく。
これが、イチヂクの本式の食べ方である。
イチヂクは毎年3月に、かなり強い剪定をする。剪定の技術も不要だし、水遣りと日当たりさえ整えば、確実に収穫できる家庭栽培に最も適した果樹だ。
スーパーに並ぶイチヂクの品種は、もっぱら「桝井(ますい)ドーフィン」。
この品種以外にも、さらに甘みの強い黒イチヂクや、白イチヂク、丸みを帯びた蓬莱柿(ほうらいし)など、いろいろとある。
ぶどうにしても、桃にしても、梨、みかん、ブルーベリー、キウイにしても、日本国内には品種が驚くほどたくさんある。
しかし残念なことに、スーパーに並び、わたしたちが目にし、口にするものは、そのごく一部だ。
国内の果物の品種と味の多様性は、素晴らしい努力と探究心といった、日本人のものづくり魂そのものといっていい。
多様性というものは流通にのりにくい。しかし、その多様性こそが、生活に彩りと変化をもたらしてくれる。
庭というものは、みずから育む、多様性と自由の、唯一の楽園なのかもしれない。
2019年9月17日
「老人のはなし」
残暑が続く、休日の午後。登山用の大きなリュックを背負って、近隣の駅から中央線の普通列車に乗り込んだ。
わたしはしかし、登山に行くわけではなかった。長野の池田町で、醸造用のぶどうを栽培している友人の収穫を、手伝いに行くのであった。
3時間以上にわたる移動の慰めに、本棚から金田一春彦「ことばの歳時記」を引っ張りだした。
かばんに詰め込んだのはいいが、車内に満ちる午後の熱気と、ガラス越しに肌を刺す西陽で、頭がぼーっとし、広げたページは一向にすすまない。
やがて、気だるく重い午睡の底に沈んで、松本に着いた。
長野駅まで結ぶ篠ノ井線に乗り換え、2駅目の明科駅で下車し、友人の出迎えた車で池田町へ。
池田町は、南北に流れる高瀬川を境に、西に永遠と連なる北アルプスの山々を眺め、東の丘陵地に醸造用のぶどう畑が点在し、盆地には、収穫を迎えようとしている、黄金色の稲田が穏やかに広がる。
丘の斜面にある友人のぶどう畑から一望する、北アルプスの清々しい姿。そして、青い空。
ほかに視界に入ってくるものは、何ひとつない。なんて贅沢な景色なのだろう。
この丘陵地は、昭和50年代までは養蚕を支える桑畑が、一面に広がっていたそうだ。
家計を助けるために、桑の木を育て、自宅で養蚕を行っていたのだ。
2階建ての家の至るところにお蚕様が住まい、そのわずかな隙間で人が寝起きをしていたという。
年に4回、桑の葉を収穫し、40日かけて4回眠り、起きている間は桑の葉を食べ続け成長するお蚕様を育てた。
行きの電車で、ぼんやりした頭で読んだ「ことばの歳時記」で、動物、ましてや昆虫に、「お」を付けて呼ぶのは、「お蚕様」以外に、「お猿」「お馬」など極めて数少ない。
それほどにお蚕様は、生活を支えてくれる大切な生き物であった、という一文を読んできたばかりであった。
ぶどうの収穫をしながら、養蚕を経験された老人の話を聞き、本に印刷されたことばが、わたしの目の前で、息を吹き返し、生き生きとした姿を現した。
製糸産業の衰退とともに、桑の木は抜かれ、新たな収入の道を求めて、丘陵地はぶどうが植えられた。お蚕様を育て、桑栽培をしてきた男性が、同じ畑でぶどう栽培に切り替えたときの気持ちはどのようなものであったのだろう?
老人の話を聞きながら、家中を満たす、お蚕様が桑の葉を食む音が、遠くから聞こえてくるようだった。
地域を支える産業の変遷で、過去の姿は影も形もなくなってしまう。
ぶどう栽培の地に、お蚕様の記憶が消えて欲しくない。よそ者は老人の話を聞きながら、過去と現在を二重写しにして、この地の匂い、風の感触を深く感じてみる。
さて、白ワインの原料となる、ソーヴィニヨン・ブランを1日で約2トン、無事に収穫した。
わたしにとっては、ぶどうの収穫以上に、この老人が土地とともに生きてきた歴史を、わずかながらでも収穫できたことが、なによりも幸福であった。
土地は、人々が生きてきた歴史そのものなのだ。
移住してきた友人たちが、この土地の歴史を、どのように彩ってゆくのだろう。
2019年9月9日
「自然界の音」
音楽というものを聴かなくなって久しい。音楽のメロディというものは、空間そのものをさらってしまう魔力がある。時をどこかに置き忘れてしまったような、時そのものが止まってしまったような、日常とはかけ離れた空間をこちらに約束してくれる、そのような魔力。
煙草の煙にように、お酒の酔いのように、日常の流れをひと時緩やかなものにする、魔法の変速機のようなものであり、少々依存症の嫌いもあり、ひとはそこにわずかばかりの救済を望んでいる。
その音楽が空間を占めるという状況が、ある時から急に息苦しいものとなってきた。
人の心や理性が編み出したメロディは、人工(アート)であり、そのアートの中に、自然を見出すことができなってきた、ということだろうか。
一日中、バッハを聴いている時があった。
たぶん、その時わたしはバッハというドラッグに犯されていたのかもしれない。
バッハの音色が、たちどころに創造する空間に、全身を浸して依存していたのだ。
今、バッハを一日中聴くことは出来ないが、風の音や、虫の音に一日中触れることはできる。耳が飽きるということがないのだ。それらは、アートではなく、自然そのものだから。
今年の晩夏は、夕立に恵まれた。
夕立の気配がすると、最高のコンサートに触れられる幸運な聴衆となって、雷の音に耳を澄ます。沸き立つ風の音に耳を澄ます。
自然が発する音は、エネルギーのうねりそのものであり、そのような自然のエネルギーが渦巻く只中で、人間が生きていることの奇跡を全身で感じるのだ。
上空で繰り広げられる、雷の光と音と振動の大迫力は、人間がどうしたって実演できるものではない。だからこそ、自然の奏でる音楽は本当に美しい。
夜中、宇宙の闇と交信をつづける、精巧で規則的な、虫たちの音。
その音に全身を預けて眠る時、わたしも同じく宇宙の闇に近づいているような気がする。
これらの音は、空間をわたしからさらってゆくことはない。
空間とともにある音であり、今という儚い時そのものなのなのだ。
わたしは、自然がみずからのエネルギーを絞り出して奏でる音に信頼を置きすぎて、アートの音楽から、すっかり遠ざかってしまっている。
2019年9月2日
「極楽は高からず」
日々、炎天下の仕事で大汗をかいているというのに、まだ足りないのか、体の芯からあるったけの汗を絞り出したくなった。その汗は、夏の間に貯めこんだ疲労や、日常に蓄積した怠惰といった澱みの汗であり、そんなものはさっさと体の外に放り出してしまいたい。
休日の午後、昼食後にやがて訪れる睡魔から逃げるようにしてスクーターにまたがり、半時間ほど走って岩盤浴のある天然温泉施設に向かった。
淡い桃色の石や、赤みを帯びた石などが敷き詰められた、室温49度の岩盤浴に30分も横になっていると、体のいたるところから汗が途切れることなく滲み出てくる。こちらの想定を優に超えた汗の量にたじろいでしまう。
休憩を挟んで小一時間、もはや澱んでいるのか何なのか分からない、無色透明な汗をかきにかいてすっきりし、露天風呂でも入ってさっさと帰るか、と思っていたのが間違いであった。
真っ白な入道雲が浮かぶ、夏の青空を眺めながらの露天風呂は、なんて気持ちが良いのだろう。
ぬるま湯に浸かりながら大空を眺め、自然の風を肌に受ける心地よさといったら。
家からたった半時間の移動でも、ひとは日常を離れて贅沢な気分を味わえるものだ――。悦に入ってそろそろ退散するかと歩みを進めると、巨大な壷のようなお一人様用ジャグジー風呂が目に入る。
壷にぷかぷか浮いて、放心している他人の様はひどく滑稽だが、試してみるとこれが素晴らしく極楽気分に浸れるのだった。
わたしの姿も同じく滑稽にちがいないのだが、そんなことはもはやこの極楽空間ではどうでもいいのだ。
どうでもいいのは、どうでもいいのだが、この極楽に浸り過ぎ、のぼせて足元がふらつく。
冷水を全身に浴びて屋外の寝椅子にしばらく横になり、平常心をようよう取り戻す。極楽もほどほどにしないと、と反省しながら、屋内風呂を突っ切って脱衣所へ向かおうとしたら、大好きなジェットバスが視野の中に入ってしまった。
「腹」「腰」「足裏」と入浴コーナーが分かれており、迷わず「腰」へ直進し、高圧ジェットを思う存分背中に浴びせかける。またしても極楽。
極楽というものは、浸りすぎると「あー、こんなことしていていいのかなー」と罪悪感すら湧いてくる。
先ほどののぼせが脳裏によぎり、ほぼ氷水のような水風呂に足を恐る恐る入れ、一気にからだを冷却する。
ほてりを吹き飛ばしたからだは、先ほどの反省さえも水に流してしまい、恍惚に浸るいくつもの顔が湯面に浮かぶ、高濃度炭酸泉へと引き込まれてゆく。
ああ、何というワンダーランド。
今夏は登山にも海水浴にも行かなかったが、わたしの夏はこれで充分だ。細かな炭酸が幾つも幾つも浮かんでは弾けるシャンパンの様な湯の中で、わたしは意外に安い人間であることを思い知ったのであった。
その後、何度も氷水とシャンパン風呂を行き来し、きりがないので後ろ髪を引かれながら、とうとうワンダーランドを後にした。
入浴料700円、岩盤浴500円、合計1200円で、休日2時間の極楽を得た。
しかも体重がおよそ2キロも減っていた。
いや、なんとも極楽、極楽。
2019年8月26日
「熟成10年のウスターソース」
いったい何年かかったのだろう。とうとう念願のウスターソースを作った。10年以上も前だろうか。保存食作りにはまっていた時期があり、図書館で「保存食」というタイトルを見つけては、何冊も借りては読み、試せるものは試してみる、ということを繰り返していた。
山椒やどくだみ、金木犀の花をホワイトリカーで漬けたり、ズッキーニやナスを酢で煮て干したものをオイル漬けにしたり、果物をシロップ漬けにしたり、手元にある素材でどんな保存食を作れるのだろうかと、闇雲に手探りしていたのだ。
しかし、本当に試したいものは別にあった。
ケチャップ、ビールにソーセージ、そしてウスターソース。
ソーセージに関しては、羊腸にひき肉を絞り入れる道具まで揃えたが、なぜかそこから先へ一向に進まず、挙句の果てには近隣のフリーマーケットで赤の他人に売ってしまった。
いずれも、作ろうと思えば素材は簡単に揃えられるものばかり。
なのに、手が出ない。一歩先へ足が進まない――。そして、月日はあっという間に10年を過ぎた。
数年前から、何度も繰り返し観ているDVDがある。
東北地方の小さな農村を舞台に、四季折々の食材を育て、調理しながら、ひとりの女性が大人へと成長してゆく姿を描いた映画「リトル・フォレスト」。
主人公は実にまめまめしく、そして貪欲に、山村で獲れる果物や木の実などを使って、さまざまな保存食を次から次へと作ってゆく。
手際よく進んでゆく調理風景を眺めながら、自分も調理している気分になり、どっぷりと映像の世界に入り込んでしまうのだ。
物語は春夏秋冬の4編に分かれるのだが、夏編で主人公は、自分の畑で取れた野菜で、ウスターソースを作りはじめた。
わたしは映像の再生を停止し、何度も巻き戻してその作り方を凝視するのだが、やがて眠気が訪れ、ウスターソースは夜の闇に溶け込んで、時は再び過ぎていった。
先日、かぼちゃのコロッケを作って、食べた。
愛知県産の旬のかぼちゃは、短時間蒸すだけで柔らかく、しかも味が濃い。
県産の豚ひき肉と玉ねぎを炒め、塩、黒胡椒で味付けし、蒸したかぼちゃと混ぜ合わせてコロッケを揚げる。
何もつけなくてもそのままで充分に美味しいが、ウスターソースとケチャップを合わせたものを少しつけても、また別の味わいがある。ああ、なんて幸福なのだろう。
その時、ウスターソースが脳に何らかの刺激を与えたのだろうか。
何年も頭の中の引き出しの奥に仕舞い込み、埃をかぶっていたウスターソース作りの願望と、現実の回路がしっかりとつながったのだ。
この夏挑戦しなかったら、多分この先何年も、ウスターソースを作ることはないだろう。
急いでレンタルビデオ店にスクーターを走らせ、「リトルフォレスト・夏編」を借り、再び何度観たかしれない、ウスターソースのシーンを見て、材料のメモを取る。
おお、我が家にあるものだけで簡単に作れてしまうではないか!
運良く、図書館から借りている「ベニシアのハーブ便り」にも、ウスターソースのレシピが丁寧に記されている。
ふたつのレシピを混ぜこせにして、失敗覚悟で挑戦してみることにする。
「材料A」
・玉ねぎ1玉
・人参1本
・セロリ1本(葉も使う)
・トマト3個以上
・にんにく1片
・しょうがひとかけ
・とうがらし1本
・昆布
・シナモンスティック1本
・クローブ数個
・ホール黒胡椒小さじ1
・ローリエ数枚
・ナツメグ、パプリカ、オールスパイスの粉各大さじ1
・クミンシード、カルダモン、マスタードシード各小さじ1
・エルブドプロヴァンス大さじ1
「材料B」
・濃口しょうゆ100cc程度
・米酢100cc程度
・粗糖
・黒糖
・塩
・玉ねぎ1玉
・人参1本
・セロリ1本(葉も使う)
・トマト3個以上
・にんにく1片
・しょうがひとかけ
・とうがらし1本
・昆布
・シナモンスティック1本
・クローブ数個
・ホール黒胡椒小さじ1
・ローリエ数枚
・ナツメグ、パプリカ、オールスパイスの粉各大さじ1
・クミンシード、カルダモン、マスタードシード各小さじ1
・エルブドプロヴァンス大さじ1
「材料B」
・濃口しょうゆ100cc程度
・米酢100cc程度
・粗糖
・黒糖
・塩
いずれのレシピにも、セージとタイムの生を入れろとあるが、我が家にはないので、タイムなど色々な乾燥ハーブをミックスした、エルプドプロヴァンスで代用する。
使用したスパイスはすべて入れる必要はないと思うが、今回は家にあるスパイスを、実験的に何でも放り込んでみる。
さて、作ってみよう。
まず最初に、野菜はみじん切り、千切り、乱切りなんでもいい。最終的に濾すことを考えて、千切りにする。
材料Aと水1リットルを鍋に入れ、ことことと煮立てないで2時間以上、煮汁が半分に煮詰まるまで火にかける。あらゆるスパイスの芳しい香りがキッチンに立ちあがってくる。
煮詰まったらザルで野菜を濾し、煮汁のみを鍋に戻す。
材料Bを、鍋に加える。しょう油と米酢はほぼ同量でいいが、かなりの黒糖を加える。
ここに、砂糖類の量を記していないのは、何度も味見をしながら、黒糖を追加しているから。ウスターソースは思いのほか、砂糖の塊であるのだ。
とろりと煮詰めたかったら、火にかけ続ければいいし、さらっとした味にしたかったら火を止めればいい。
自分好みのウスターソースを作るのだから、判断を下すのは常に自分の舌であることを忘れずに。何が成功で、何が失敗かなど関係ない。美味しければそれでいいではないか。
鍋いっぱいに煮た野菜類は300ccほどに濃縮されて、透明の瓶へ納まった。
考えていたよりも、ほとんど作る手間がかからないウスターソース。
カレー作りのようで、カレーよりも簡単。ジャム作りのようでもあるが、しかしもっと奥深い。
両者の調理技法が、ウスターソースという本流に合流したようで、なんとも感慨深い。
「その時」というものは、こちらが思いもしないときにやって来ると思っていたが、時はこちらの成熟加減をしっかり見計らって、満身創痍でやって来るのかもしれない。
父親の作りすぎた夏の真っ赤なトマトが、我が家の冷蔵庫に入りきらないほど大量にある。
さあ、次はトマトケチャップね、と耳元で時がここぞとばかりにささやいている。
2019年8月19日
「野暮ったくて何が悪い」
室内の温度計を見るたびにぞっとする真夏の午後。何をするにも億劫なのに、空腹は昼食!昼食!と胃壁を叩いて叫んでいる。
冷し中華にするつもりでいたが、なぜか無性に真っ赤に燃えるスパゲッティー・ナポリタンが食べたくなった。
わたしは、ナポリタンをずっと馬鹿にしていた。
ケチャップで真っ赤に味付けしただけの、繊細さのかけらもない極太麺のナポリタンを、パスタというものの仲間には絶対に入れたくなかった。
概ね、男性というものはどうしてケチャップ味が好きなのだろう?
オムライスに、チキンライス――。
幼い頃口にしたお子様ランチの味わいを、いつまでたっても忘れることができないのが、男というものなのだろうか。
我が父もご多分に漏れず、ナポリタンと聞くと幼児のように目をきらきらと輝かせ、パスタに絡みついた真っ赤なケチャップを、我が血なり!と猛烈な勢いで飲み込んでゆく。
食欲旺盛と真っ赤なナポリタンはしっかりと肩を組み合い、向かうところ敵なしと、他を圧倒するのだった。
猛暑の下、我が胃袋は、やわな味ではとてもじゃないが適わない!と音を上げたのだろうか。
視覚、味覚、そして胃袋は、曖昧さというものをすべて撥ね付け、真っ赤なケチャップ味のナポリタン!と明瞭な言葉を、わたしに向けて猛直球で投げてきたのだ。
冷蔵庫から玉ねぎとしなびたピーマン、冷凍庫からベーコンを取り出し、フライパンでケチャップとウスターソース、塩、胡椒でしっかりと味を付ける。その傍らで、太麺のパスタを茹でる。
何も考えなくていい、あるものだけで調理すればいい、従うべきは我が空腹の声のみ――。
真っ白な大皿にそびえる、真っ赤なパスタの山。その上には、雲がかかるように目玉焼きが乗っている。
いただきますと言ってから、ご馳走様でしたと手を合わせるまで、ものの数分。
ナポリタンは、野暮ったくて、すぐさま元気が沸々と湧いてくる、力強い夏の味なのであった。
2019年8月8日
「真夏の太陽に導かれて」
だらだらと目覚め、そのままベッドで本を読む休日の朝。窓の外は眩しい夏の空が広がり、室内で寝転んでいるわたしに何か言いたげな様子である。
これではいけないと身を起こし、汗をかきながら朝の雑事を済ませてしまうと、先ほどまでもたれ気味だった胃腸は快活に動き出し、空腹という文字が全身を一気に駆け巡る。
さて、今日は何をして過ごそうか?
明日は月曜日なので図書館が休館だ。
今日のうちに借りたい本を借りておかないと、6月から続けているイタリアの旅が中断してしまう。急いで身支度をし、スクーターのエンジンをかける。
室内で眺めていた強烈な夏の光は、外に出てみれば意外に爽やかで、スクーターで風を切ると、夏とからだが一体化したような気分となって心地が良い。
陽に焼け付くアスファルトから立ち上がる熱気のせいだろうか、無性に分厚い肉が食べたくなり、肉塊の料理をあれこれと想像しながら、炎天の下を一気に走り抜ける。
図書館の1階で、中学生の絵画作品が展示されていた。
冷やかしのつもりで覗いたのだが、夏の光のように眩しい10代の感性に圧倒されてしまった。
若さとは、こんなにも濁りがなく、真っ直ぐで、眩しいものだったのか?
空と海と小さな島を描いた単純極まりない絵の前で、言葉を失い立ち尽くしてしまう。
大人には絶対に描けない絵というものがある。
稚拙さというものは、なぜこんなにも人の心を打つのだろう?
広い海と空の青、そして白い雲に、茶色い島。ただそれだけなのに、夏の海と空は、間違いなくわたしの目の前にきらきらと鮮やかに輝き広がっている。
居間をぐるりと囲む白い壁にこの絵を掲げたら、わたしはいつでも浜辺に駆けて行けるに違いない。
絵画作品を見て、久しぶりに心が揺れ動いた。
真夏の太陽は、寝室で寝転んでいたわたしを、夏の海と空の青さ、そしてかつて自分にもあった、瑞々しい感性というものの前へ引きずり出し、目覚めよ!と頬を激しく叩くのであった。
2019年8月2日
「Jam Session」
数年前、ジャム作りで生計を立てられないか、と真剣に考えた時があった。果物と砂糖だけでなく、洋酒を加えたり、2種の果物を合わせてみたりと、ガスコンロの前で実験的なことをして楽しんでいた。
生の果物の新鮮な味を、そのままジャムに封じ込めるのは難しい。
保存のために砂糖を加え、火にかけて少し煮詰めるだけでも、爽やかな新鮮さは急速なスピードで消えてゆき、代わりに、その果実が隠し持っていた酸味や苦味などが明るみに出てくる。
まさにそのさじ加減が、ジャムの成果を左右する。
ジャムなんかにしなければ良かった!と後悔することも多いのだ。
のん気な気分で他ごとをしながらジャムを作ると、天罰が下ったかのように、なぜか必ず失敗する。
頻繁に味を見ながら、ここぞ!というタイミングで火を止めなければ、ジャムの味は取り返しの付かないものとなる。
一秒一秒、刻一刻と、鍋の中の果実は味と姿を変化してゆく。
ジャム作りは、作り手と果実による、一発勝負のジャムセッションそのものなのだ。
バナナ、いちぢく、苺、ぶどう、杏、梅、りんご、梨、柿、柑橘類、ヤマモモ、ユスラウメ、キウイ、カリン、パイン、ブルーベリー、ブラックベリー、ジューンベリー、桃――。
色々な果物でジャムを作ってきたが、最近ちょっと珍しい果物でジャムを作ってみた。
パパイヤだ。
黄色く完熟しているのに、甘みも旨みもまったくないパパイヤ2個を持て余している。
食べるのは苦痛だし、捨てるのも勿体無いので、ものは試しでジャムにしてみた。
ミキサーで果実を細かくし、重量の20〜30パーセントのグラニュー糖を振りかけて、果汁がでてくるまでしばらく置いておく。
果汁が出てきたら鍋に入れ、5〜10分程火にかける。
その間、もちろん何度も味見をして、いつ火を止めるかのタイミングを見極める。
出来上がったジャムの鮮やかな色彩に、まず驚く。そして、そのジャムの味に、二度驚く。
あのパパイヤの嫌なクセは、どこへ行ってしまったのだ?
廉価なバニラアイスクリームに添えて口にしてみると、お互いの欠点を補い合うように調和して、とても良い味になる。
これは、元の素材の味を見事に超えた、ジャムの数少ない成功例のひとつだろう。
わたしは、この偶然の成功例に調子づき、次はどんな果物をジャムに仕立て上げようかと、嬉々として考えを巡らしている。
愛知県産の色鮮やかなドラゴンフルーツが、農産物直売所に並んでいる。
いつも気になって、気になって仕方がない程、それは見事なドラゴンフルーツなのだ。
まさかこれをジャムに?!
いえ、それはやっぱり出来ません――。
小心者のジャム作りは、何度も小石につまづきながら、新たな発見を夢見てつづいてゆく。
2019年7月29日
「イタリアを旅して」
6月からずっと、イタリア各地を旅している。ヴェネツィアに始まった旅は、ミラノやインペリア、リグリアの寒村ポッジ、サルディーニャ島、ナポリ、シチリアへと続く。
海辺に行けば、山間も行き、イタリアのひだを縫うようなこの旅は、急くことなく、悠々と贅沢に過ぎてゆく。
さて、これからどの土地に行き、どんな出会いをするのか――。
ムートンを掛けた籐椅子にからだをたっぷりと沈め、本のページをゆっくりとめくる。
矢島翠の「ヴェネツィア暮し」を読んでいた。
梅雨の雨音の中、運河の都がかもす匂いや湿気、水音や住人が響かせる生活音が、ページをめくるたびに、肌に生々しく伝わってくる。
けれども、この古都にもっと足を踏み入れたいのに、何かが足りない。
何が足りないのだろう?
街に住む人の声が、吐息が、この本からわたしの耳に届いてこないのだった。
真っ赤なレインコートで全身を覆い、スクーターで雨の中、図書館へ走った。
求めるものは、内田洋子の「対岸のヴェネツィア」と、同氏のイタリアエッセイ集数冊。
そそくさと帰宅し、イタリアに住む様々な人間の人生に触れるために、ふたたびヴェネツィアの旅を続けた。
もう何年も前に、内田洋子のイタリアエッセイは何冊も読んでいた。
当時はこれで充分だと思っていたが、ヴェネツィアに足を踏み入れたら、彼女がイタリアで見出した、様々な人間模様に、再び触れたくなったのだ。
様々な土地で、様々な事情を抱えて生きる人々の様子を、たった数冊の本を開くだけで伺い知ることができるなんて、なんと贅沢な話なのだろう。
人が集まれば、ワインの栓を開けて飲み交わす。そこにわたしも同席して、白や赤ワインを口に含み、酔った気分になる。
そして、そのままベッドの夢の中へと潜ってゆく。
6月にはじめた旅は、8月に入っても終わりそうもない。
イタリアの長旅が終わったら、そのまま東南アジアのミャンマーへ向かう予定だ。
チェニイの「喜びの木陰」と「漁師」が、ページを開かれるのをじっと待っている。
2019年7月25日
「生活に重石を」
小さな冷蔵庫で、6年ほどやりくりをしていた。ひとり暮らしで110リットルの冷蔵庫が小さい、というのは贅沢な話ではないか?しかし、わたしにとっては非常に切実な問題であったのだ。
夏の暑さに、のどを潤そうにもスイカが入らない。
たまご1パック分のスペースがないので、冬の間は常温保存。
キャベツ1玉、大根1本などもってのほか。
実家でお惣菜を分けてもらいたくても、常に辞退。
大きな冷蔵庫が欲しい!
心の中でこだまする想いを通り過ぎ、今夏も父親の作りすぎたトマトやピーマンが、次から次へと我が家にやってくる。
室温に置いておくとすぐに痛んでしまうので、トマトはトマトソースにして冷蔵保存してしまうが、ピーマンに至っては調理の手が回らず、もはや夏を彩る観賞物となっている。
ああ、何も考えずに野菜を買い、もらい、冷蔵庫にぽいっと放り込みたい!
積もりに積もったストレスは、今夏最高潮に達していた。
気分も、天気もまったく晴れない、職場の休憩時。
同僚が、45リットルの冷蔵庫が不要になったと言う。長年の想いがとうとう天へ届いたのだろうか?一目散にこぼれ話に飛びついた。
段取りはものの5分で片付いてしまい、翌日には小さな冷蔵庫が我が家にやって来た。
冷蔵庫の隣にならぶ、もう1台の冷蔵庫。
新入りだが、中古の冷蔵庫に、早速あるったけの野菜を詰め込むと、何もかもがすっきりとした。
冷蔵庫の中だけでなく、台所までもが――。
手製のキャスター付き木製収納ボックスに乗せた、新たな冷蔵庫。
台所が狭くなることなど、はじめから諦めていた。
しかし、こちらの予想に反して、新たな収納空間は、何もない空間を生み出し、仕舞いには台所の動線までをも改善してしまった。
小さな冷蔵庫は、わたしが持て余していた野菜だけでなく、積もり積もったストレスまでをも軽々と飲み込んでしまったようだ。
物と空間、そして生活の関係性は面白い。
何も置かない、すっきりとした室内空間が魅力だと思っていたが、そういう空間を実現できるのは、精神的に充足した修道士のような人間か、無趣味の人間か、仕事が忙しくて室内空間にまで手が回らない人間か、徹底したミニマリストではないだろうか?
どの分類にも属さないわたしのような凡人は、空間に納まる物の重力によって、地球の外へ放り出されないように、この世とのバランスを保っているのだ。
2019年7月22日
「〜Frank Gehry フランク・ゲーリー建築の話をしよう〜」という書物にある彼の言葉に勇気をもらっている。
 この言葉に何時も励まされる。
この言葉に何時も励まされる。
ゲーリーのような大きな人生やスケールで仕事は出来ないけれど僕には僕の人生がある。そうやって今も必死に歯を食いしばっている。
自分がいいと思っているものを、わかってくれる人がいると信じることが大事だ。万人受けする野暮ったい建物を造ることもできるけれど、それは人を見下すのと同じじゃないだろうか。自分に才能があるかどうかなんてわからない。
人より優れているかどうかも解らない。ただやるべきことを見つけ、実行するだけだ。気に入ってもらえたらラッキーだけど、全員にすかれることなんてありえない。好きだと言う人と同じくらい、嫌いだと言う人がいる。だから全力を尽くしたら、あとは執着しないことだ。僕はそうしてる。
人より優れているかどうかも解らない。ただやるべきことを見つけ、実行するだけだ。気に入ってもらえたらラッキーだけど、全員にすかれることなんてありえない。好きだと言う人と同じくらい、嫌いだと言う人がいる。だから全力を尽くしたら、あとは執着しないことだ。僕はそうしてる。
 この言葉に何時も励まされる。
この言葉に何時も励まされる。ゲーリーのような大きな人生やスケールで仕事は出来ないけれど僕には僕の人生がある。そうやって今も必死に歯を食いしばっている。
2019年7月12日
「からだが知っていることを信じる忍耐」
扁桃腺が腫れ、からだの至るところが痛み、何もする気が起こらず、2日間ただひたすら寝ていた。病院で抗生物質を処方されるのは嫌だし、何より病院に行く気力もなく、数年前に知人から頂いた梅肉エキス(青梅をすり下ろし、その絞り汁を煮詰める、大変手間のかかる貴重品)と、梅を塩漬けする際に出る梅酢をお湯で割り、朝と晩に薬のつもりで飲んでいた。
抗菌性の高い梅肉エキスを信じるのも、信じないのも自分次第。
そして、今回は何にも頼らず、ただ梅と睡眠にすがった。
野生動物は、からだの調子が悪いとき、ただひたすらじっとしているそうだ。
じっとする、ということは非常に忍耐がいる。
世の中は回りまわっているのに、自分だけ廃人のようにベッドの上にいる。
色々な夢を見るし、色々なことを考える。
動物はいったい、何を考えじっとしているのだろう?
動物のようにからだを丸め、なるべく何も考えず、静かな静かな夜の闇の底に沈む。
からだはまだ少し痛むが、2日でのどの腫れはほぼ引いた。
何もする気が起きない2日間、食欲を満たしてくれたものは、トウモロコシと桃。
トウモロコシが安いときに2、3本まとめ買いし、家に帰ってすぐに塩茹でする。
1本を3等分に切り分け冷蔵保存しておくと、空腹を感じたときにすぐに口にすることができ、重宝する。それが、今回、我が胃袋を救った。
そして、完熟した桃4玉。
のどを甘く冷してくれる、これ以上の薬はあるだろうか?
3日目の今朝、やっとからだが動き、掃除機をかけてから、朝市の買出しに出かけた。
トウモロコシ3本とスモモ、オクラをかごに入れ、そぞろ歩けば新鮮なバジルが目に付いた。
深々と吸い込むその香りが、不調なからだにすっと入り込んでゆく。
バジルなんか買っても使い切れないのではないか、という心の声を、香りの力は完全に圧倒してしまった。
帰宅してから、いつまた倒れてもいいように、急場をしのぐ食料保存をする。
冷凍しておいたかぼちゃのペーストを牛乳で温め、濃厚なかぼちゃスープを仕込み、冷蔵保存。かぼちゃの冷たいスープは、美味しいだけでなく栄養満点で、満腹感もある。
トウモロコシも茹でて、冷蔵した。
オクラは茹でて冷蔵するつもりが、茹でたはなから食べ尽くしてしまった。
そしてバジル。
調べてみたら、精神のリラックスにとても良く、また抗菌性が高いハーブとある。
ああ、からだは本能的に必要なものを知っているのだ。
父親が栽培したトマトで仕込んだトマトソースが冷蔵保存してある。
これにわしづかみにしたバジルを放り込み、今夜の夕食はパスタだ。
濃厚なトマトソースとバジルの香りは、回復してきたからだの中に、新鮮な血液のように循環しはじめる。 ああ、美味しい!
2日間のからだの不調で痛感した、旬の食材の恵みと、ありがたみ。
もっと謙虚に、もっと素直に、自分を支える環境と向き合わないといけない。
心身が弱ったときに開き読む「ベニシアの庭づくり」から、静かな音楽を聴くように、そのことを学んだ。
「かぼちゃスープのレシピ」
1.かぼちゃの皮と種を取り除き、できるだけ薄くスライスする。
2.味わいに深みを出すために、人参も好みで同様にスライスする。
3.鍋にバターと野菜が浸る程度の牛乳を入れ、野菜が柔らかくなるまで、ふたをして弱火で蒸し煮にする。
4.野菜が柔らかくなったら、荒熱をとり、ミキサーにかける。
5.ピューレになった野菜に、牛乳と顆粒スープ、塩を加え、好みの濃さに調整。
冷蔵すれば、冷たいスープになる。
6.ピューレした野菜を冷凍しておけば、いつでも美味しいスープがいただける。
1.かぼちゃの皮と種を取り除き、できるだけ薄くスライスする。
2.味わいに深みを出すために、人参も好みで同様にスライスする。
3.鍋にバターと野菜が浸る程度の牛乳を入れ、野菜が柔らかくなるまで、ふたをして弱火で蒸し煮にする。
4.野菜が柔らかくなったら、荒熱をとり、ミキサーにかける。
5.ピューレになった野菜に、牛乳と顆粒スープ、塩を加え、好みの濃さに調整。
冷蔵すれば、冷たいスープになる。
6.ピューレした野菜を冷凍しておけば、いつでも美味しいスープがいただける。
2019年7月8日
 設計事務所に所属する建築士には、3年以内に1回の定期講習が義務付けられています。先日その講習に参加し、朝から晩まで座学…更に、終わりには講習考査がありました。
設計事務所に所属する建築士には、3年以内に1回の定期講習が義務付けられています。先日その講習に参加し、朝から晩まで座学…更に、終わりには講習考査がありました。設計事務所の管理建築士講習を5年に1度の事務所登録更新の度に受講したり、監理技術者の講習を受けたり…毎年同じような講習を受けている感が半端ありません。これで毎年高額な受講料を搾取する、生産性のない社会傾向に辟易します…。
2019年7月3日
「価値観を鍛えよ、拾われるための落し物」
月に1回、近所のスーパーへ、鉄道の落し物販売がやってくる。落し物の王道である傘に始まり、帽子に靴、かばん、電子辞書、時計、眼鏡、スカーフや財布などが、ずらずらっと屋外の仮設テントの下に並ぶ。
なんでこんなものを落すのだろう?と思い眺めれば、自分もかつてどれだけマフラーを駅のホームや階段で落しただろうか、と過去を振り返るのである。
潔癖な人などは、どこの誰が使って落したかわからないような不明中古品は、買おうともしなければ、触れるのも嫌に違いない。
事実、使用感と生活感に満ちあふれた中古品を目にしてしまうと、持ち主はいったいどんな人であったのだろうと想像を膨らませ、遂には触れた手をうわっと離してしまうということもある。
しかし、数年前から、わたしは鉄道落し物販売で、掘り出しものを買う癖がついてしまった。
30代の中頃までは考えられなかったことだ。
好奇心と観察力の旺盛な母親が、鉄道落し物で面白い品を見つけ、安価な買い物をしてくるのがきっかけであっただろうか。
若い頃は、所在不明なものへの不信感が強く、出所がちゃんとしていて、他人の保障が付いていないと安心できないという頭の固さと、経験値の低さがあった。
きっと、鉄道落し物など馬鹿にしていたに違いない。
今はどうだろう。
馬鹿にするどころか、鉄道落し物を楽しんでいる。楽しむばかりか、生活の潤いにも一役買っている。
これが年を重ねるということなのだろうか。
それとも、所有しているお金がたんに少ないというだけの問題なのだろうか。
どちらにしても、わたしはそれを大いに歓迎している。
物の価値ほど不確定で、多様なものはない。
自分の目と心が「良し!」と思えば、出所などなんだっていいのだ。
今日は、冷やかすだけのつもりが、大変な散財をしてしまった。
足元からすでに夏休みがやってきたような、レインボーカラーの新品のゴム草履、100円。
ここで終わるはずが、普段見もしない時計コーナーに行ってしまった。
職場で使える時計があるかな?という軽い興味が、あっちの時計、こっちの時計へと視線が移り行き、何度も腕にはめたり外したりしているうちに、ひとつの時計に心がくぎづけになってしまった。
時計の表面には「riki」、裏面には「riki watanabe」と印字されている。
数字が大きくて見やすく、ベルトはとても柔らかい皮製だ。見た目の大きさを裏切る、とても軽い時計で、姿がクールで美しい。値札に手書きで800円とある。
わたしはじーっと考え込んでいる。
何を考え込んでいるのかといえば、時計はすでにあるのだ。
生活防水のない、980円で購入したポップなデザインのとてもとても軽い時計。
しかし、この軽いポップさと対極にあるアクセサリーとしての時計も欲しい。
そんなことを、屋外のテントの下で、ひとりじーっと考え込んでるのである。
そして、買った。
使い古されたものは、緊張感がなくていい。
ベルトの皮はすっかり柔らかくなり、使用感がとてもいい。以前の持ち主はきっと丁寧に使っていたに違いないという確信めいたものが、この時計からにじみ出ている。
メンズ物なので、腕にはめているとブレスレットのようにだらんとたわむ。
時計が刻む時間と、重みに縛られるのが嫌いなわたしには、こんな時計の方が性に合っている。
鉄道落し物販売で、わたしは、わたし自身の価値感がいかばかりのものなのかを、試しているのかもしれない。
2019年6月25日
「魔女の秘薬か、宝石か」
500グラムほどの赤紫蘇の葉。台所に山のように積まれた植物の葉を眺めていると、自分が昆虫か、仙人か、魔女になったような気分になる。
しかし、この気分はまんざら気分だけではなさそうだ。
なぜなら、今からこの大量の葉を煮出して、赤紫蘇シロップを作るのだから。
家で一番大きなステンレス製の大鍋を取り出して、1リットル強の湯を沸かす。
そこへ、水洗いした赤紫蘇の葉を鷲づかみにして、放り込んでゆく。
一度ではとても入りきらない量なので、湯の中で葉がしんなりしたら、葉を鷲づかみにして放り込むということを繰り返す。
全ての葉を投入してから15分以上、くつくつとエキスを煮出す。
鍋の中の液体はどんどん色彩を深めてゆき、香りもたってくる。
もうこれ以上エキスは抽出できない、というところで火を消す。
葉は取り出すが、荒熱が取れたらしっかり絞って貴重なエキスだけを鍋に戻し加える。
鍋の中に残されたものは、どす黒く気味の悪い液体のみ。
洞窟の中で仙人が、もしくは深い森の中で魔女が掻き回していそうな液体そのものだ。
このぞっとする色彩の液体に、1キロ強のグラニュー糖と2カップ程の酢、そしてひとつまみ程度のクエン酸を加える。
すると、童話の中のお姫様が口にした飲み物はこんな色だったのではないか、というようなそれはそれは魅惑的な色彩の液体へと変化する。
紫でもない。
赤でもない。
ピンクでもない。
魅惑の色そのもの。
長期保存をするのであれば、砂糖を1キロ以上入れて砂糖濃度を充分に上げておく。
加える酢の種類は何でもいいが、味にパンチが効くので、わたしは米酢を使っている。
酢を加えないと、ただ甘ったるいだけの気持ちの悪い飲み物になってしまう。
クエン酸を少量加えるのは、味わいがすっきりとするから。入れすぎるととても飲めたものではなくなってしまうので、あくまでも味をみながらひとつまみずつ。
クエン酸がなければ、レモン果汁で代用できるだろう。
砂糖、酢、クエン酸、いずれも少しずつ加えながら、自分の好みの味わいに調整してゆけばいい。
難しく考えずに、魔女になったつもりで、自分のフィーリングを信じて楽しんで欲しい。
赤紫蘇シロップが冷めたら、葉に付いていた細かな砂などを取り除くために、漏斗に油こし紙を重ねて瓶へ移し替える。
出来上がった赤紫蘇シロップは、水や炭酸で2倍以上に薄めて頂きます。
水で薄められた色彩は、見とれるばかりの美しさと美味さで、一気に2杯飲み干してしまう。
今日も、美しい赤紫蘇が枝付きで店頭に並んでいる。
どうしても買わずにはいられないし、シロップを作らずにはいられない。
これは一種の病だと思っているが、宝石を買う病に比べたらずっとましではないだろうか。
宝石の美しさを自分の手で作り出し、それを一思いに飲み込んでしまえるのだから。
宝石にしても、赤紫蘇にしても、その色彩は人の心を魅了する。
人の心を動かしてしまう色彩の力とは、エネルギーそのものではないだろうか。
魅惑的な赤紫蘇シロップは、魔女の秘薬であり、危なげな宝石の姿でもあるようだ。
2019年6月19日
 ベルギーの左官材料モールテックスの講習を受けた。モールテックスを塗った部材が空間に1つあるだけで、空間の価値は極端に跳ね上がる。
ベルギーの左官材料モールテックスの講習を受けた。モールテックスを塗った部材が空間に1つあるだけで、空間の価値は極端に跳ね上がる。魅了されて二年。ようやく講習と購入ルートにまでたどり着いた。材料を仕入れ、自分の設計に使いたい…たったこれだけの事だが、二年を費やした。(笑) もはや、情熱だけが建築人として生きるために残された最後の力。
人手不足は弊社の左官屋さんも同じで、とても「高い授業料を払って講習を受けにいってください」とは言いにくく…致し方ないので、塗れるようになるための実技講習を自らバリバリ受けたのです。

 材料の配合や施工方法、ケースによる材料選択や注意点、揃える道具など、とても多い情報量…講師の方の実技を携帯片手に動画撮影しながら必死にメモる。
材料の配合や施工方法、ケースによる材料選択や注意点、揃える道具など、とても多い情報量…講師の方の実技を携帯片手に動画撮影しながら必死にメモる。そして塗る。
ひたすら塗る。
小手をひたすら洗う。
施工中の「北区西味鋺の家」にどうしても取り入れたくて、タイトスケジュールの中にブッキングしましたが、また1つ納得できる事柄に出会えた。こういうことをコツコツ積み上げるしかない。才能がない人間が食っていくには。
2019年6月18日
「眠ってはならない、覚醒する6月」
うかっとしていると、のちのち後悔するのが6月。梅雨だと言って、ぼーっとはしていられない。
新生姜や山椒の実、梅を1年分仕込む、大切な月なのだから。
店頭に現われたと思ったら、いつの間にか姿を消しているのが旬の生産物。
きれいな新生姜を見つけたら迷わず購入し、すぐに処理する。
皮を剥き、繊維に沿って薄切りしたら、沸騰した湯の中へくぐらせる。
笊にあげて水分をきり、温かいうちに甘酢へ漬け込む。
新生姜の甘酢漬けは、散らし寿司や冷やし中華に欠かすことのできない保存食だ。
大量に仕込んでおけば、年中美味しい散らし寿司を楽しむことができる。
山椒の実は、傷がなく張りのあるものを手に入れたい。
沸騰した湯で柔らかくなるまで茹で、水切りしたら冷凍保存する。
ピリッとした辛さが、料理のアクセントとなる。
梅仕事に関しては、6月4日のコラムに紹介した通り。
常温で梅シロップは仕込まないと断言したものの、やはり美味しい梅シロップが飲みたい。
カビを発生させないためには、果汁をいち早く抽出することが重要だ。
そこで、小梅と大梅を計6キロ冷凍し、2瓶へ3回に小分けして仕込んでみた。
最近は気温が30度を超えない涼しい日が続いているのと、冷凍梅を入れるたびに瓶内が冷やされるためか、今のところ果実は発酵せず、カビも発生せず、平穏無事に果汁抽出中だ。
6月はこれで終わり?と思ったら大間違い。
とても大切で、素敵な台所仕事が待っている。ほう葉寿司作りだ。
農産物直売所に、青々として大きなほう葉が並ぶと心が揺れる。
まず、じーっと見つめ、手に触れ、うーんと考え、やいっと買ってしまう。
ほう葉寿司の魅力は、毎年作る度に進化と発見があることだ。
具材に決まりはない。
大切なのは、全体の味のバランスと、ほう葉を開いたときの感動。
ほう葉という小さな舞台で繰り広げられる物語を、いかに自分らしく演出するかなのだ。
5枚130円で購入した、つやのある美しいほう葉。
冷蔵庫を覗くと、茹でた破竹、ヤングコーン、みょうがの甘酢漬け、卵、絹さやがある。
冷凍庫には、茹でた実山椒、焼いてほぐした塩鮭、鯛のでんぶが保存してある。
常備する新生姜の甘酢漬けと、干し椎茸で、役者はいとも容易に揃ってしまった。
破竹は、干し椎茸の戻し汁としょう油、みりんでしっかり味を付けて煮る。
ヤングコーンは茹でて、甘酢に漬ける。
卵は砂糖を加えた金糸卵に。
実山椒はしょう油、酒、みりんでさっと煮る。
干し椎茸を戻し、しょう油、酒、みりん、砂糖で煮る。
絹さやはさっと色良く茹でる。
散らし寿司もそうだが、甘み、酸味、旨みのバランスが命なのだ。
椎茸の旨煮と、金糸卵、鯛でんぶの甘み。
新生姜とみょうが、ヤングコーンの甘酢漬けの酸味。
実山椒の辛味。
塩鮭と破竹の旨み。
甘いものはしっかりと甘く、酸味と旨みを明確にする。そして、色彩のバランス。
これらが舞台上でどのように展開するのかを考え、味と色彩を添えてゆく。
時間と手間をじっくりかけた作り手の愛情と、多様な味と色彩、そして6月の恵み。
すべてがほう葉に包み隠され、観客の手のひらで幕が上がるのを、ひたすらじっと待っている。
さあ、眠ってなどいられない。
心とからだ、すべてを覚醒して、6月の豊潤を丸ごと飲み込んでしまうのだ。
2019年6月12日
「全身に喜びを浴びて」
雨が大地を濡らす6月。植物は緑の濃さをますます深め、鳥たちは喜びの声を際限もなく響かせる。
自然が満ち足りているその懐の中、
雨滴る色とりどりの紫陽花をこの手で切り、花瓶へ命を活け直す。
その時、歓喜のため息がわたしの口からこぼれ落ちた。
幸せの瞬間とはこういうものなのだろうか。
わたしを取り囲む、今という時間と環境すべてが互いに交感し合い、
握りしめたらこぼれてしまう、わずか一瞬の出会い。
God bless you.
6月の雨音に絡み合い、幸福の吐息が、ふとした瞬間に頬へ触れる時、
わたしは全身で喜びを飲み込み、ふたたび大気へ歓喜のため息を返礼する。
2019年6月4日
「心と、空き瓶の準備はできている」
昨年購入したグラニュー糖の総量は、約40キロ。すべては、この季節から始まるのだ。今年は小梅は買わない、そう心に決めていた。
昨年、カリカリ梅を初めて作ったものの、嗜好性が合わないのか、途中で完全に食べ飽きてしまった。なので、今年は小梅を見ても何の動揺もなく、容易に目の前を通り過ぎることができるはずだった――。
仕事の休憩時、心優しい同僚が、口の中に放り込んでくれた一粒の小梅の梅干。
大梅にはない爽やかな甘みと、口の中で負担にならないその小ささが、暑い日の塩分補給にぴたっとはまった。
揺るがぬはずの信念は、ぐらぐらと音をたてて崩れ落ち、数日後、2キロの小梅を手に入れた。
家に戻ってすぐに小梅を洗い、竹笊にあげて水切りをする。
弱冠熟し足りないので、皮の柔らかい美味しい梅干に仕上げるために、黄色く追熟させてから塩漬けに取り掛かる。
今年は、完熟した南高梅を待ってから梅干を漬けようと思っていた。
昨年、同僚と手に入れた熟し切って捨てる寸前の南高梅。
30年の経験がある彼女が仕上げた梅干しは、ふっくらとして立派な美味しいものであった。
片や初心者が作った梅干の何とも貧相なこと。雨に打たれては干されることを繰り返していたら、果肉がげっそりとしてしまった。
今年は昨年の反省を踏まえ、2年目の梅干作りに挑戦となる。
まずは、小梅で腕を慣らしておいたほうが良さそうだ。
小梅の収穫から南高梅の収穫まで、約1ヶ月。
この間に収穫される大梅で、毎年大量の梅シロップを仕込む。
砂糖漬けにして数週間、常温でゆっくりと梅エキスを抽出する方法は、味も色も格段に素晴らしい。しかし、高温の我が家では、梅にカビが発生して止む無く処分という経験が何度もあるため、この方法はやめた。
秋から冬にかけて、保存食作りで一歩も譲らない「時長」。
しかし、最も敬遠する「時短」に、夏だけはすべてを委ねてしまおう。
洗った大梅の水分を取り除いたら、なり口を取って炊飯器に入れる。梅の半分の重量のグラニュー糖を入れて「保温」ボタンを押すだけ。 12時間ほどで砂糖は完全に溶け、梅シロップが仕上がる。
梅を取り除いたシロップを鍋に入れ、沸騰させて冷ましたものを保存する。
我が家は、このシロップを常温で数ヶ月保存している。
この梅シロップを水で薄めた飲み物は、何の抵抗もなく火照った身体のすみずみにまで浸透し、太陽光に抗う力を再び生み出してくれる。
冬の間に用意した何本もの空き瓶が全て満たされるまで、大梅を手に入れ、炊飯器で梅のエキスを抽出する日々が1ヶ月続く。
赤紫蘇が店頭に並べば、赤紫蘇シロップもせっせと作り保存する。
この2つの飲み物さえあれば、どれだけ暑くても何とかやっていけそうな気がするのだ。
山のようなグラニュー糖が、次から次へと鍋の中で溶け消えて、やがて命の飲み物へと姿を変える。
ああ、甘くて危険な季節が、これから始まるのだ。
2019年5月28日
「過激に平和な、寒天ポンチ」
わたしの職場は植物を相手にした、太陽直下の肉体労働。最近の急激な気温の変化に、同僚は皆一様に疲れ気味の様子だ。暑さで疲れがピークに達する午後の休憩時。男性陣の機嫌は悪く、わずかな火の気でもあれば、すぐさま導火線に引火して爆発してしまいそう。
この様な非常事態時、最も効果をあげる救済策――。それは、お手製の冷製デザートだ。
甘くて冷たいものは、火照った心身をやんわりとリセットしてくれる。男性陣の表情も、先ほどに比べて少し和らいできただろうか?
そこで、職場の平和維持とわずかな楽しみのために、頭と財布をひねりながら、思いつくまま夏場のデザートを作っている。
毎年夏になると、業務用のかき氷機が雑然とした休憩所に据えられる。
2リットル入りの巨大なかき氷シロップが数種類ストックされ、銘々が好き好きに、氷の甘さと冷たさで身体にこもった熱を発散する。
しかしこの業務用シロップ、どれだけかき氷を食べても、ワンシーズンでなかなか使い切る事ができない。
かさ張るシロップのパックは、冷蔵庫で幅を利かせながら冬越しをし、春を通り過ごし、とうとう2度目を夏を迎えることとなる。
今のところ邪魔くさいだけで、何の役にも立たず冷蔵庫に入ったままの、いちごの赤、メロンの緑、日向夏の黄色の3パック。
これらをじーっと眺めていたら、ふと思いついた。
夏だけに許される、過激で平和なデザートが作れそうじゃない?
それぞれのシロップを水で薄め、粉寒天を加えたら、火にかけて冷やし固める。
ゼラチンの比較にならないほど寒天の固まりは早いので、気持ちは気楽だ。
赤、黄、緑に固まった3色の寒天を、サイコロ状に切り分ける。
鍋に水とグラニュー糖を加え、しっかりとした甘みのシロップを作る。
ボールに冷やしたシロップと三ツ矢サイダーを入れ、そこにサイコロ状の寒天を加える。
すると、アジアの露店に迷い込んだような極彩色のデザートが現れる。
普段はあえて手を触れない人工色の赤、緑、黄色が、強い太陽光の下では急に親しみを覚えるのは何故だろう。
幼い時の縁日の楽しみ――。
安っぽくて、からだに悪い味というものは、夏の暑さと妙にしっくりとくる。
職場では、この中にドラゴンフルーツとバナナをサイコロ状に切ったものを加えた。
ここでわたしは声を大にして言いたい。
ドラゴンフルーツは、デザートにおける名脇役であるということを。
白地に黒ゴマのような種が点在したドラゴンフルーツの色彩と、そのやや淡白な味、しっかりとした歯ごたえは、人工色で目がチカチカする、子供のおもちゃ箱のような寒天ポンチの過激さにブレーキをかけて、バランスの整ったデザートへ昇華させる。
バナナでは駄目。キウイフルーツでも駄目。パインでも駄目。あれも駄目、これも駄目。
使い切れないかき氷シロップの救済デザートが、ドラゴンフルーツの美しさにうっとり見とれてしまうデザートとなってしまった。
もちろん、ドラゴンフルーツが入っていなくても充分に美味しくいただけるデザートだ。
炭酸が抜けた方が全体の味馴染みがいいので、冷蔵庫で数時間寝かせてから食べていただきたい。
隣に座る同僚が、ズズズーっとシロップを飲み干したのを見たとき、蕎麦つゆを飲み干すお客を眺める蕎麦屋の気持ちと一つになった。
わたしはこのデザートの色彩と味がとても好きになってしまったので、母親が毎年6月に招待されるホームパーティに、この過激な寒天ポンチを是非もたせようと思っている。
好奇心旺盛な母は、自分の手間が省けることもあり大賛成だ。
夏は始まったばかり。職場の休憩所から、この夏どんな過激で、平和なデザートが生まれるだろう。
2019年5月20日
「がらくた山に響く、天使の声」
近所の小さなスーパー。今年も段ボールにガラクタばかりを山積みに、店頭で所狭しと赤十字のバザーをやっている。
あらゆる物が支離滅裂に陳列されている姿にうんざりし、いつもさっさと素通りして店内の買い物を済ませるが、今年はふと足を止めた。
ブルーシートの上に、今様でない小ぶりな染付けの花柄のティーカップ6客とシュガーポット、ミルクポットのワンセットが無造作に並べてある。
金縁が剥げてないので、手放した持ち主はほとんど使っていなかったのではないだろうか。
共に汗する職場の女性陣と、休憩時に優雅なひとときを彩るには持って来いの品だと思い、ボランティアをしている60代と思しき女性に値段を聞く。
「そうねー、250円でどうかしら」。
250円とは、彼女の頭の中から何の根拠もなくポッと沸いてしまった数字だろう。
他人が無償で提供した品を売りさばくのがバザーなわけで、値段は売り手の人生経験と想像力、そして何よりも善意によるしかないということだ。
わたしは、「安すぎる」と内心ほくそ笑みながら、優美で華奢なそのティーカップセットを購入した。
これから店内で買い物だというのに、荷物はすでにかさ張って重い。
ついでの冷やかしに、陶磁器を無茶苦茶に突っ込んだ段ボールに視線を移す。そこに、埃まみれになった蛸唐草に松竹梅の染付け皿が大小2枚。
最近の陶磁器にはない製品の良さがある。たった今購入したティーカップセットと、もしや同じ持ち主ではないだろうか。
先ほどの女性に値段を尋ねると、一瞬考えたのち、「50円」と言葉を返した。
彼女にあるものは良心なのか、想像力の欠如なのか、もうわたしには分からない。あるのはただただ感謝のみ。
更に重くかさばる荷物を抱え、店内の買い物へ進もうとしたところ、書籍の山が目に付いた。
「ジョエル・ロブションのすべて」。
イノシシやウサギなど、一生調理することはないだろう食材の取り扱いなどを記した、分厚い辞書のようなフランス料理本が紛れている。しかも新品だ。
今日これで3度目となる、かの女性に値段を問う。
「そうねー、100円でどうかしら」。
わたしの目からは涙がこぼれそうになる。この人の美しい心が変わらないうちにさっさと100円を手渡し、足早に店内へ姿を消してしまう。
帰宅後判明したこの本の定価は8000円だ。
あの女性は、人間の姿をいっとき借りた天使であったのだろうか?
今や夕餉の食卓に欠くことのできない染付けの皿。
マヨネーズを添えただけの茹でブロッコリーが、この皿に盛り付けると何故か殿様ご膳へと化けてしまう。
染付けのティーカップは、昭和60年代、鳴海製陶が輸出向けに製造したものであった。
この小さなティーカップは、初夏へ向かおうとしている5月の気候そのものの爽やかさで日々を彩る。
かつて陶器の勉強をしていたにも関わらず、染付けの底力というものがここまで力強く、しなやかなものであるということを今更ながら痛感するのであった。
埃にまみれたがらくた山を、決して侮ってはならない。
2019年5月13日
「雑草遊泳」
初夏へ移り変わろうとしている季節の変化は、顔を見あげて目に飛び込んでくる空の青さや、山の緑の冴えなどから全身で感受することができるが、目線を落とした足元でも、初夏の訪れを賑やかに知らせてくれるもの達がある。「雑草」とひとくくりで片付けている植物群。
一ヶ月以上前まで、まったく興味をそそられることのない対象物であったが、ある日職場で除草作業をしているときに悟った。
ほぼ毎日雑草と取っ組み合っているのに、その雑草の何たるかを学ぼうとしないとは如何なることか。職業意識の欠如は、自らの恥じを晴天の下に晒した。
そこからが早かった。
図書館から何冊もの雑草図鑑を借り、夜な夜な重たいまぶたを引きずりページをめくった。
知らないことを知るためには、対象の詳細な観察から始める。
ある植物の名が知りたい。花や葉の特徴、その色をしっかりと目で捉え、図鑑と見比べる。これが簡単そうで意外に難しい。
同じ黄色い花でも、微妙に花弁の数や形状が異なり、よく目を凝らして調べないと、足を踏み入れた雑草迷路から出るに出られず、立ち往生。
このような迷路の行ったり来たりを日々繰り返しているうちに、やがて雑草を一瞥するだけでその名称が自然に口からこぼれるようになる。
迷路の行き先に光が照らされたら、あとはその光を真っ直ぐに進んでゆけばいい。
知らないということは、単なる怠惰であったのだ。
最近は目線が下に落ちっぱなしだ。さて、ここにはどんな雑草が生えている?
今まで姿を見せなかった小判草(コバンソウ)が、脇に姫小判草を従えて、太古の姿を留めた昆虫のような実をブラブラとぶら下げている。
一体どんな深い悩みがあったのか、うな垂れっぱなしの蕾をよっこいしょと持ち上げ、春紫苑(ハルジオン)がようやく笑顔の花を咲かせた。
鬼田平子(オニタビラコ)はますます背を伸ばし、上空に小さな黄色い花火を次々に打ち上げている。
ひょろひょろとどこまで行き、何をしようとしているのか、松葉雲蘭(マツバウンラン)は薄紫の小花を誰にともなくささやいている。
小さな黄色い宝石をあたり一面にまき散らし、満足そうにしているのは米粒詰め草(コメツブツメクサ)。
若さで輝やく肌を自信たっぷりに晒す仏の座(ホトケノザ)。その隣で、姫踊り子草(ヒメオドリコソウ)は素肌をそっと隠してしおらしくしている。
足元で幼児の笑い声を絡ませてくる大犬のふぐり(オオイヌノフグリ)。
はこべと和蘭耳菜草(オランダミミナグサ)、耳菜草、蚤の襖(ノミノフスマ)の一族は、一軒一軒戸を叩いて家主と対面しないことには、誰が誰だか一向に埒が明かない。
地に埋もれながらドキッとするような視線を投げかける蛇苺(ヘビイチゴ)。
石器時代の名残のような武器を担いだ雀の槍(スズメノヤリ)は、一体何からの襲撃に日々そなえているのか。
小が大を飲み込む存在感がある、庭石菖(ニワゼキショウ)の雅。
歩道の脇やちょっとした空き地、どこにでも雑草という生命力溢れた植物は生えている。
身をかがめて小さな世界を凝視すると、時間はいっときマクロな世界へと飛躍する。
遠く見あげる宇宙の広さは、目線を落としたすぐ足元にも豊かに広がっている。
2019年5月7日
「我が身を守る、夕食貯金」
仕事から帰った夜、わたしは夕食の支度に、まな板と包丁を一切使わない。こう言うと、とても悲壮感漂う粗末な夕食をとっているように思われるだろうが、ご飯とお味噌汁、おかず3品は必ず食卓に並べる。
多いときは5品というときもある。
冷凍食品やレトルト食品、スーパーのお惣菜は、我が家では歓迎されない客人であり、わたしは魔法使いでも、手品師でもない。
それでは包丁とまな板を使わずに、どうやって夕食を用意できるというのか?
夕食の支度は10分もあれば完了してしまう。
椎茸と刻みねぎを具に入れた香ばしい八丁赤味噌汁。
刻みねぎとゴマ、黒酢、しょう油で和えた、喉越し良い沖縄もずく。
人参と椎茸、油揚げがたっぷり入った優しい甘みのひじきの煮物。
一晩味付けして、しっかり味のついた手羽元の照り煮。
人参、きゅうり、春雨の中華風酢の物、バンサンスー。
希望とあらば、菜花やほうれん草の和え物も即座に用意ができる。
すべて冷蔵庫内のガラス容器、もしくは冷凍庫の保存パックから、染付けの皿や漆器にぱぱっと移し変えるだけ。
これらおかずを直径45センチの円卓に所狭しと並べ置き、もぐもぐと口を動かしながら色々な食材の味と食感を楽しむひととき。
一日中、屋外でからだを動かす仕事をしていると、カレー、うどん、パスタだけといった単品夕食に、肉体と頭が納得しない。
酸味、甘み、苦味、旨み、冷たさ、温かさ、そして食感や色彩が豊かに混在した和食は、心身の隅々まで充実感をみなぎらす。
健康を維持するためにもバランスのよい食事が必要だが、毎晩仕事から帰って一から準備をするのは、ストレス以外の何物でもない。
そこで休みの日をフル稼動し、夕食貯金に取り掛かる。
煮物やお味噌汁に使う出汁は、まとめて1リットル作って冷蔵保存。
さば、むろあじの厚削り節と羅臼昆布をたっぷり水に入れて一晩置き、翌日弱火でゆっくり煮出すといい出汁がとれる。味のいい出汁は、何よりも豊かな食事を保障する。
椎茸やしめじなどのきのこ類は刻んでざるに干し、冷凍保存。煮物やお味噌汁を作るとき、冷凍庫から取り出し、ぽいぽいっと出汁に放り込むだけでいい。便利なだけでなく、味も濃縮されていいことずくめだ。
油揚げは使いやすいサイズに切って冷凍保存。
菜花やほうれん草などの葉物も、新鮮なうちに茹でてしまい、使いやすいサイズに切って冷凍保存。水に入れて解凍すれば、和え物やスープなどにすぐ使え、不足しがちな緑黄色野菜を積極的にとることができる。
もずくは、パックから取り出したらすぐに調味料で和えて冷蔵保存。幾つも個包装されたもずくは冷蔵庫だけでなく、ごみもかさばり、味も好きでないので買わない。
ねぎは数日分を刻んで、いつでも使えるように冷蔵保存。
サヤエンドウやパセリなども、茹でたり、食べやすい大きさにちぎって冷蔵保存。
朝食用の塩鮭は、まとめて5切れグリルで焼いてほぐし、冷凍保存。瓶詰めの鮭フレークより経済的で、何より味が良い。
ひじきの煮物やバンサンスーなどのおかずは5食分ほどまとめて調理し、冷蔵保存。
人参を刻むとなったら、朝食用の人参ラペ、ひじきの煮物、バンサンスー用にまとめて4本ほど刻んでしまう。
更に波に乗り、バンサンスーのきゅうりを刻んだついでに、もう一本きゅうりを刻んでポテトサラダも作ってしまう。
買い物から帰ったら座ってお茶など飲まず、一気呵成に次から次へと食材の処理を済ませてしまうのだ。
このように、下処理した食材やおかずを、鮮度を失わずに5日間ほど冷蔵保存するためには、プラスチック容器ではまず無理な話で、ぜひともガラス容器を取り揃えたい。百円ショップで売られているもので十分だ。
道具選びも味と時間を保証するものだということを、失敗を重ねた経験者が強く主張するところである。
休日に貯めこんだ夕食貯金があれば、包丁とまな板を持ち出さなくでも、すぐに3、4品のバランスのとれたおかずが食卓に用意できる。
自分が持ち合わせている時間と、冷蔵・冷凍庫のサイズ、家事技術やお財布事情もろもろを天秤にかけて、自分なりの夕食貯金をこつこつと続けてゆけば、毎日の食卓に豊かさと彩りが生まれるだろう。
2019年4月26日
「植物は、其処でじっと待っている」
面白い出来事があった。名古屋東部にある職場でのこと。
除草作業をしていると、ここにシロバナタンポポは自生していませんかと中年の男性客が声をかけてきた。在来種のシロバナタンポポをどうしても実際に見て、カメラに収めたいらしい。
白いタンポポ?
今までの人生で、わたしはこの目で黄色でないタンポポを見たことがあるだろうか?
まるで記憶がないし、残念ながら職場にシロバナタンポポは自生していない。
男性は所在無く立ち去ってゆき、シロバナタンポポもわたしの人生から遠のいてゆくかと思われた。
数日後、犬山祭に母と出かけた。
大変陽気のよい一日で、のんびりと桜を愛でながら、犬山城の周りを流れる川沿いをそぞろ歩いていた。西洋タンポポやカラスノエンドウなど、お決まりの雑草がのびのびと背を伸ばしている。
桜の樹の足元に、ピンクや黄色の花々が小さな歓声をあげている景色をじーっと眺めていると、ぽつんと一本、白いタンポポが咲いている。 わが目を疑った。
あのシロバナタンポポが、時を遡って目の前に姿をあらわしたのだ。
母親にことの次第を伝えると、先ほど群生している場所があったとさらりと言う。
桜色の空気というものは、いとも容易く時の流れをかきまわしてしまう。
西洋タンポポの黄色い群れの中で、このシロバナタンポポはいつまで咲き続けることができるのだろう?そんな心配をしながら、川沿いの道を再び進んでゆくと、蔓状に伸びた枝から白く涼しげな小花が咲いている。
母もわたしもその愛らしい花木の名を知らない。
後日職場で調べようと写真に収め、二人のそぞろ歩きは永遠の川のごとく一日流れ続けた。
それから数週間。
職場で棚作りしているアケビが、薄紫色の小さな花を無数に咲かせている。
なんとも言えず可愛らしい姿で、数本の蔓を切り落として花瓶に活けた。
今まで桜の花を活けていた職場のロビーに、一転して爽やかな初夏の風が吹き抜ける。
ところで、わが職場のアケビは実がつかない。
自家不結実性のアケビは、結実するために異品種のミツバアケビなどを混植する必要がある。
職場に混植していたミツバアケビは絶えてしまったため、残されたアケビは結実することなく、ただ可憐に花を咲かせているわけだ。
アケビの品種を知るために、インターネットで様々な画像を検索していてふと思い当たった。
犬山城の川沿いで撮影した名称不明の蔓性植物は、まさにアケビそのものではないか。
職場のアケビの花は薄紫色だが、犬山で撮影したアケビの花弁は白色。
柵ごしに遠い姿を眺めたので、今までまったく気がつかなかったし、撮影したことすら忘れていた。
遠くに流れ去ったと思われた時間が、緩やかにその流れの向きを変えた。
名古屋にあるわたしの職場と犬山城には、どうやら目では見ることのできない時空の川が流れているようだ。
2019年4月19日
「桜の下で舞う日本人」
桜という完全な舞台装置を、日本人がいとも容易く生活に取り入れてしまったこと。それは日本人の死生観にあるのではないかと思う。
何の変哲も、色も香りもない、記憶の片隅にも残らないありふれた町並みの中、人は目的地へ向かって歩みを進め、車はスピードを上げてどこかへ急ぎ立ち去ってゆく。
昨日と今日を隔てる違いやずれというものは何ひとつなく、壁紙のようにぺらりとめくれてしまいそうな恐ろしく平ぺったい日常という風景が、ある日突如としてむくりと立ち上がる。
満開の桜から伸びる美しい指先が、日常に流れる時間をくるりとかき回す。
先ほどまで四肢を固めていた景色は酔いでふらつき、その渦中にいるわれわれも天地を忘れて酔いに酔う。
あの世とこの世までもが花色の指先にかき回され、もはや両者を隔てる境はない。
わたしの前面は生の空気に触れているが、背後は死の空気に触れているかもしれず、自分の知っているつもりの所在地が、なにかとてもあやふやなものになり、ではそれが不安かといえばまったくそうではなく、その所在なさが妙に心地よい。
歩いているのに地面に触れている感覚はなく、景色を見ているつもりですでに景色と溶け込んでおり、見上げた桜はみずからに咲く花となる。
遠く離れているものが肌に触れるほど傍らに近づき、今という時は霞にまぎれ、重力に縛られた日常の生は、羽衣をまとって自由自在に時空を舞い上がる。
わたしたちは、どういうわけだか本能的に知っている。
忙しない生の時間を潜り抜け、桜の木の下からいとも軽やかに、あらゆる隔たりを解き放つあの世へ戯れることを。
2019年4月15日
「波打ち際の椰子の実」
椰子の実が波に流されて、何の因縁か、ある日遠い異国の砂浜へたどり着く。やがてその実を拾い上げる人がいるのか、それとも人の手にも触れられず再び波にさらわれてゆくのか――。
最近の我が家には、椰子の実は流れ着いてこないが、次から次へと熱帯の果実がどっさりと流れ着く。青パパイヤ、青バナナ、未熟なスターフルーツにレンブ。
いずれも、ひと手間かけないととても口にできないものばかりだ。
一方、冬季は食料庫として襖を閉ざしたままの北側の一室には、加工しても一向に減る様子のないハッサクの山がそびえ立っている。
我が家と頭と時間の砂浜は、もはや果実の波に浸食されつつある。
果実は流れ着いた砂浜でじっと待っている。
わたしが動き、近づき、手に取り、それを口にすることを。
その気配を感じながらも、他にも生活はすべきことがいくつでもあり、果実を波打ち際から拾い上げることは後回しになってしまう。
しかし、果実にも鮮度というものがる。
私の時間にも鮮度というものがある。
椰子の実が再び漂流を始める前に、この手で拾い上げてやること。そのタイミングというものはどこにあるのだろう。
スターフルーツを加工処理しなくても、生活は何事もなく続いてゆくし、青バナナを苦心して食べようとしなくても日本人の食卓は何一つ困らない。これら淡々と続いてゆく生活の隙間に、わたしが椰子の実と出会う波打ち際というものが隠れているようだ。
毎日続く家事や仕事で心身が一杯一杯になっていると、この波打ち際がまったく見えないし、打ち寄せる波音も聞こえず、潮風を肌に感じることもできない。
心の暇を見失うということは、「見るべき目」「聞くべき耳」「感じるべき肌」を完全に見失うことであった。
ザザザー、ザザザザー――。
波が浜に打ち寄せる音が遠くから聞こえてくる。
背中には砂糖がぎっしりと詰まったリュックを背負い、右手に包丁、左手に鍋を持って、生活の鬱蒼たる森から余暇たる波打ち際への小道をかきわけてゆく。
次から次へと我が砂浜に流れ着く果実を、この手で拾い上げるために。
2019年4月5日
「木材について学びませんか?」
 5月25日に弊社協力業者の材木屋さんによる「東白川村森林ツアー」があります。皆様いかがでしょうか?僕も家族と参加しようかな…って思ってます。
5月25日に弊社協力業者の材木屋さんによる「東白川村森林ツアー」があります。皆様いかがでしょうか?僕も家族と参加しようかな…って思ってます。日本の木材の流通は近年大きく変化しました。角に丸みのある1等や2等という等級のヒノキ材や杉材など見向きもされなくなり、角がピンとある特等しか流通しなくなりました。また海外産の材木や集成材も主流になり、日本の林業は衰退の一途をたどっています。
間伐材をうまく使いながら森林を維持していける仕組みを勉強して、もっとおおらかに、もっと寛容性のある家づくりが今後日本では見直されるべきです。
植林をしたり製材工場を見学したり、木材について1日学べます。ぜひお子様と一緒にご参加ください。参加希望の方は弊社までお問い合わせメールをお送りください。皆様のご参加をお待ちしております。
2019年2月21日
「物は回りまわって塵となる」
我が家では、新聞は3回生まれ変わる。まず、新聞としての本来の目的である新聞記事を読む。その後、新聞は「紙」としての機能を果たすべく2回活用される。読み終えた新聞を、そのままのサイズ「大」と、それを2分割にした「中」、さらに2分割した「小」の3種類のサイズに分類する。
「大」は、白菜や大根など大きな野菜を包むためのもの。
「中」は、葉物やニンジン、きゅうりなど、クッキングペーパーで包んだ小ぶりの野菜を、保存性を高めるために更に包むためのもの。
「小」は、野菜くずや、食器の汚れを拭った米ぬかなど、台所から排出されるごみを包んで捨てるもの。
これでは、新聞は2回の使用で終わってしまうではないかと思われるだろうが、頼りがいのある丈夫な新聞を、野菜を包み終わった段階でむざむざと捨てるわけにはいかない。
台所の扉を開けたベランダに吊り下げた物干しハンガーに、湿り気を帯びた新聞を乾かし、再び「小」へ分割して台所ごみ処理用に利用する。 ここまで新聞を活用すると、清々しい気分にさえなる。
ちなみに、野菜を包んでいたクッキングペーパーも、同じように食器の汚れ拭きとして再利用する。クッキングペーパーはとても便利な台所用品だ。便利だからこそ気をつけて使わないと際限がなくなるので、洗った野菜は布巾で拭うようにした。青森にある「森のイスキア」で佐藤初女さんが実践されていたことを本で知り、見習ったことだ。
ビニール袋も汚れのひどいものは捨てるが、1回野菜を包んだだけのものなどは、水洗いして干し、ごみ処理用に使う。
そもそもビニール袋自体を使うべきではないのだが、習慣は自らの行動を汚染し、それに甘んじてしまっている。社会の仕組みが整うのを、受身で待っていてはいけないのだ。
生活にはリサイクルできるものがたくさんある。
使用済みで裏白の用紙は、もちろんメモ帳へ再利用。自分で作った簡易メモ帳は気軽い使いやすさで、もう何年もメモ帳など買っていない。
使用済みの麻ひもやビニールひもなども、捨てずに小さく結んで保存する。新しいひもを切らなくても、使用済みのひもで大概の目的は果たせてしまうのでとても重宝している。
食べ終わったゼリー容器や、綿棒が入っていたケース、ふたのない瓶、おかずの入っていたプラスチックパック――。視点を変えれば、再び活用できるものは身の回りにたくさんある。
これらを収納するスペースの問題もあるが、すぐになんでもかんでもゴミ箱へ捨ててしまう行為は、見ていて美しいものではない。
物を捨てることはとても簡単だが、活かすことには知恵と工夫が必要になる。あらゆるものは限られた資源なのだ。
最近は、サランラップを使うことも気が引け、何か代替品はないかと考えている。
江戸時代、紙は何度も再利用された。手紙はメモ書きに使われ、さらには襖の破れを塞ぎ、紙縒りにさえなった。
着物は徹底的にリサイクルされ、着物をほどいた糸さえも再び使われた。
そういう行為を貧乏くさいという人がいるが、そうだろうか?
暮らしに知恵と工夫を伴おうとしない行為のほうが、貧乏で気の毒なことだとわたしは思う。
2019年2月13日
「ああ目出度き、サラダかな」
立春から1週間が過ぎ、やっと雛人形を飾ることができた。1年のうちわずかな期間しか陽の光を浴びてもらうことができないので、もっと早く迎えてあげたいのだが、自らが生みだす日常のざわつきが、おおらかな心の余裕をすっぽりと覆ってしまい、支度が遅れてしまった。
実家から譲り受けた、お内裏様と三任官如。
母方の祖父が買い与えてくれた木目込みのお人形は、佇まいが非常に優雅で表情に少しの棘もない。暗闇の中で1年の大半を過ごしてきたというのに、何の恨めしさもなく優しい微笑みを投げかけている。
見ているだけで心のざわつきがほぐれてゆくのは、雛人形が春の光を放っているからだろうか。
色彩とは春の代名詞だと思っている。
お姫様が身に着けている十二単は色彩の海原だ。三任官如は紅白をまとい、お姫様の色彩を見事に引き立てている。
「ああ目出度きかな、春光の到来よ!」とお人形を飾り、色彩を余すところなく享受しようとした日本文化のなんと高尚なことか。着物を日常から手放し、洋装が常になった我々日本人は、色彩の目出度さと有り難味をどれだけ享受しているのだろう。
1月も中旬を過ぎたあたりから、体が突如として生野菜を欲するようになった。色々な野菜と味を、様々な食感で、モリモリムシャムシャと馬車馬のように食いつきたいのだ。
そして、毎晩翌朝のサラダを仕込む「盛り盛りサラダ」作りが始まった。
今朝のサラダ。
・一口サイズにちぎったレタス
・輪切りしたブラックオリーブ
・キャロット・オニオンラペ(ケイパー、ショウガ、レモン、蜂蜜で漬けた物を常備)
・乱切りトマト
・さっと湯がいた絹さや
・ちぎったパセリ
・マッシュルームのマリネ
・乱切りしたゆで卵
・サイコロに切った木綿豆腐
これにパルメザンチーズ、塩、みかんシロップ、オリーブオイルをかけて頂く。日によって、ここにちりめん雑魚やサラダ寒天、蒸しジャガイモが加わることもある。
このサラダは色々な食感、味の混在だけでなく、緑、赤、白、黄色、黒、オレンジといった色彩の饗宴が眠っていた脳をはっと目覚めさせる。
自分が全く意識もしなければ操作もしていない体の本能というものは凄いなと思う。甘み、苦味、酸味、旨み、渋みで停滞していた冬の体を目覚めさせ、目出度き色彩を全身に取り込み、体の深部から春の芽吹きを猛烈に促しているのだから。
「わたしは知らない、けれどもわたしは知っている。」
無意識はぼーっとしている意識に、見えないものをしっかり見るようにと懸命に声を張り上げる。それが、わたしにとっては「盛り盛りサラダ」という形になって現れた。
まだまだ寒い季節は続くが、土壌の深くに、体の深部に春の芽吹きが生まれようとしている。
灰色の、暗い色彩を脱ぎ捨てて、目出度き色彩を余すことなく享受しようではないか。
2019年1月30日
「瓶詰めにした太陽光」
色彩を失ってしまった灰色の冬空に、太陽の光のごとく輝く樹木がある。八朔、伊予柑、夏みかん、甘夏などの柑橘樹だ。
果皮は厚くて剥きにくく、果実は酸味と種があるために、生食の好き嫌いがはっきりと分かれる柑橘類ではないだろうか。
しかし、この負の特性が錬金術の手にかかると、黄金の食べ物として見事に生まれ変わる。
これら柑橘の分厚く、苦味のある果皮は、食用としてママレードや砂糖漬け(ピール)に加工ができる。ママレードは果皮と果肉のジャムで、砂糖漬けは、果皮に砂糖液を染み込ませたものだ。生食だと苦くてとても食べることができない果皮が、人の手と砂糖と時間によって魅惑的な食べ物となる。
いずれも作り方は様々だが、簡単に説明してみよう。
ママレードもピールも、果実と果皮に取り分けたら、果皮だけを沸騰する湯のなかで何度か煮る「湯でこぼし」を行う。苦味を取りながら、同時に厚い果皮を食べやすいように柔らかくするためだ。
しかし、これら柑橘の特性でもある苦味をすべて取り除いてしまうと、ただの甘ったるい食べ物になってしまうので、適度な苦味を残しながら湯でこぼすという経験値が必要になってくる。
さて、簡単に噛み砕ける柔らかさになった果皮。
ピールは果皮についた白くて厚い綿の部分を残し、数日間かけて砂糖液の濃度を徐々に高めて浸透させてゆく。火にかけた鍋で1時間程で仕上げるスタンダードな方法もあるが、時間と砂糖に任せっきりの「放牧スタイル」が何か神秘的であり、また性にあっているので昨年からこちらの方法を採用している。
充分に砂糖が浸透した果皮は、太陽の光が凝縮したような透明感と輝きがある。
これを乾燥させて、グラニュー糖やチョコレートをコーティングして菓子としてもいいし、乾燥させないでパウンドケーキなどの具材にしてもいい。
今冬にせっせと作って冷凍しておかないと、来年の2月分までパウンドケーキにピールを入れることができなくなってしまう。
未来の喜びを貯金するために、一日という時間は台所であっという間に流れてゆく。
ママレードは、果皮についた綿の部分が苦味につながるのですべて取り除き、残った果皮を千切り、もしくはみじん切りにする。これを果実と砂糖で煮込むだけ。とろみ成分のペクチンを抽出するため、袋と種はお茶パックなどに入れて一緒に煮込む。
と、簡単に書いてはいるが、作り手や砂糖の量、煮込み時間、果実を絞るのかそのままにするのかなどによって仕上がりは千差万別。
しかも、毎年同じ味のママレードに仕上がらないというのが面白い。
「今年も太陽の光をこの手で煮詰めたよね?」と自問自答しながら、出来上がったママレードの瓶詰めを、太陽の光に透かしてうっとり眺める。
瓶には、「2019年ママレード」ではなく、「2019年太陽光」とラベルを貼ったほうが、自然界の神秘を讃えるようでいいかもしれない。
2019年1月18日
「透明な世界」
実家のトイレで桐島洋子の「聡明な女は料理がうまい」(1970年)を読んでいたのは、高校生か大学生の頃だろうか。そこには未知の世界と生活の知恵がぎっしりと詰まっていて、「いつか、わたしもこんな台所を持ちたいな」という憧れを抱いて本を手にしていたことを覚えている。
一人暮らしを始めたのが25歳だったろうか。
台所には、乾物などを入れた瓶がいくつか並んだ。理由は分かっている。桐島洋子の本に影響されたからだ。
影響力とは不思議な力を持っていて、一度生活に取り入れてしまうと、それは生まれたときからそうしているのではないかという程、当人には当たり前の習慣、常識として定着してゆく。
そしてそれから15年以上たった今、場所を変えた我が家の台所には瓶が溢れている。
当時の影響力は、自らの樹木となり枝葉を広げ大きく成長した。
前回のコラムで年末年始の収納整理について語ったが、この際我が家にはいったい何本の食品保存瓶があるのか数えてみた。
ざっと150本。内訳は以下のとおり。
「乾物」
刻み海苔・大豆・切干大根・ひじき・海草・春雨・刻み昆布・出汁昆布・かつお節・ごま・黒ごま・米ぬか
「調味料」
ブラウンシュガー・グラニュー糖・氷砂糖・上白糖・粗糖・黒糖・てんさい糖・粗塩・片栗粉・カレー粉
「香辛料・ハーブ」
セロリ葉・ローリエ・唐辛子・花椒・マスタードシード・シナモン・八角・コリアンダー・クミンシード・フェンネルシード・パプリカ・ウコン・カルダモン・オールスパイス・クローブ・ナツメグ・カトルエピス
「茶」
麦茶・紅茶・ほうじ茶・ジャスミン茶・中国茶・ココア
「手作り薬用チンキ」
柚子チンキ・枇杷チンキ・ドクダミチンキ・アロエチンキ
「手作り果実酒」
梅酒・金木犀酒・みかん酒・ナイアガラ酒・イチゴ酒
「手作り保存食」
カリン蜂蜜漬け・梅干し甘漬け・新生姜の甘酢漬け・トマト水煮・ズッキーニオイル漬け・梅シロップ漬け・レーズンラム酒漬け・イチヂクワイン漬け・栗渋皮煮・梅酒漬け梅のシロップ漬け・ザワークラウト・ラッキョウ漬け・レモン蜂蜜漬け・杏シロップ漬け・柿シロップ漬け・杏ジャム・りんごジャム・ぶどうジャム・ゆすらうめジャム・イチヂクジャム・カリンシロップ
「手作り調味料」
割り下・中華ドレッシング・ゴマだれ
これら瓶が、冷蔵庫、台所の引き出し、ワゴン、押入れの中で出番を待っている。
そして、使い終わったワインや洋酒、調味料の空き瓶も、同じく次の出番がくるまで押入れの中で眠っている。
なぜ瓶にそこまでこだわるのか?
・まずは保存性が高いこと
・割れない限り、使用耐年数が長いこと
・中身が見えること
・耐酸性があること
・縦長なので保存スペースを取らないこと
しかし一番の理由は、瓶から透けて見える食品の姿が美しいからだろうか。
いや、そこに生活を支える自分自身の姿を見て、満足をしているのかもしれない。
2019年1月8日
「家と頭の中を整理する」
時間と気力が充分な年末年始、家の収納を大改革して頭の中と生活を見直した。日常生活で生まれる大小様々なストレスは、放っておくと膿となって心身を蝕み、健全であるべき生活を不安定にしかねない。
そのために、日々自分を苛立たせている家の中の事象を洗い出し、その解決法を探ることが大切になる。
さて、我が家はひとり暮らしなのに物がいっぱい。
空き瓶、空箱、瓶詰め保存食、貯蔵食品、書籍、登山道具、買い集めた靴や服に鞄。
押入れと納戸はこれ以上の隙間はないという飽和状態。
押入れの奥に入れたものなどすでに頭の記憶に微塵もなく、一年経ってやっと陽の光を浴びることの繰り返し。このような押入れの明暗な出し入れが、自身を日常的なストレスにさらしていることに気がつき、解決策を模索していた。
イケア長久手店へ毎月ドライブがてらにバイクを走らせ半年以上になる。
買って、使って、納得し、通うたびに新たな発見がある場所だ。単なる購買意欲とは少し訳が違う。
使い勝手が良く汎用性の効くものは、シンプルなのに、形状、機能がとても良く考えられている。
このような製品はデザインが頭の中でこねくり回されたのではなく、生活の実感から生み出されたプロダクトデザインであるということがしみじみと感じられる。
その中でも、一度買って半年の間に5回もリピート購入したものが、3段式のワゴン「HORNAVAN(ホールナヴァン)」。
真っ白なただのキャスター付きの棚で、値段は1499円。サイズは26×48×77センチ。
使い勝手がよく、家中この棚で埋め尽くしたいくらいに惚れ込んでいる製品だ。
普通、家具は設置スペースを取るので部屋が狭くなると考えるが、それがあるからこそ部屋が広く感じるという家具もある。
我が家はキッチンに3台設置し、瓶詰めにした調味料や保存食、お茶、医薬品、水筒、根菜類、ごみ分別、掃除道具などを収納している。
ワゴンなので収納したものは丸見えだが、これでいい。見えないと何がどこにあるのか分からず、探す時間やストレスが増すだけでなく、収納している物の存在意味さえなくなってしまう。
これだと、調味料の買い置きは一目瞭然。梅干や新生姜の甘酢漬けなど、朝食の副菜や各種お茶もぱぱっと手を伸ばして取り出せるので、無駄な動きがなくなった。
たかがワゴン、されどワゴンだ。
玄関横の納戸にも2台設置し、トイレットペーパーや水、タオル、家の手入れ道具などをスッキリ収納。
このワゴンに取り付けられる小物入れ「SUNNERSTA(スンネルスタ)79円」で、暗闇に閉じこもっていた物が陽の光へ次から次へと姿を現す。
家だけでなく、自分の体の中にもさわやかな風が吹き抜ける心地だ。
収納を考えることは、自分が営む日常生活を考えることと同じことだ。
自分に必要なものや不必要なもの、自分の価値観などが理屈ではなく現実そのものとして見えてくる。住まうとういことは生活を整理することで、それは生活技術ということに繋がるのかもしれない。
今回、我が家の収納改革をするにあたり、改めて食品関連のものが多いことを認識したが、それらは自分の生活を潤してくれる趣味そのものであり、自分の分身で大切なものであると歓迎できたことは意外な出来事であった。
他人には無駄な空き瓶も、わたしには保存食を作るための大切なツール。
物の所有を否定するのではなく、肯定して前へ進んでゆくことのできる収納改革を手助けしてくれたイケアのプロダクトデザインの哲学に、身をもって感謝する年末年始であった。
2019年1月1日
「年始のご挨拶」
新年おめでとうございます。本年もよろしくお願いいたします。昨年の10月末からジョギングを始めました。その日の都合に合わせて、6km〜8kmを走っています。最初は全く走ることが出来ず、歩きたくなったりペースが遅かったりしましたが、2〜3日走って休息日を設けて2ヶ月も経つと1kmあたりのペースも少しずつ上がってきました。
40歳を超えて急激に代謝が悪くなり、中性脂肪とコレステロールが溜まってきたことに対しての嫌悪感からジョギングを始めましたが、最近ようやく走ることが「楽しい」と思える気がしています。(笑)
こうやって少しずつ…牛歩のように、建築的思考や個人的な心の内部も向上して行けるよう今年も頑張っていきます!!